脳梗塞の種類は大きく3種類! 症状ごとに知っておくべき特徴とは?
脳梗塞は脳内の動脈が狭くなったり、血栓で閉塞してしまったりすることで発症します。脳梗塞の範囲が大きいと、さまざまな身体上の障害につながる可能性も。では、記事の中で詳しくみていきましょう。高齢ドライバーによる事故が増加傾向! 脳卒中の予防には脳ドックがおすすめ
 9
9
タクシーの高齢運転従事者による事故比率が増加
都内で起きている交通事故は年々現象していますが、高齢者事故の割合は年々増加傾向にあります。

2020年度は新型コロナウイルスの影響で人の流れが少なくなったことで、事故件数も高齢者事故の割合も減っています。
しかしまたタクシーやバスなどの公共交通の利用が増え始めると、今後は全体の事故に対して、ますます高齢者の事故の割合が増えていくことが予測されます。
全国のタクシードライバーの平均年齢は?
全国のタクシードライバーの平均年齢は、60.1歳。 もっとも平均年齢が高い福井県では、67.1歳となっています。
バスやトラックの運転従事者でも、若者の車離れによる、高齢のドライバーが増えている現状があるようです。
脳卒中による重大事故が周囲に大きな影響を与える

高齢になるほど、脳卒中のリスクは高まります。
そのためか、高齢の運転従事者が脳卒中を発症することで起こる事故が、大きな社会問題になる事例が散見されます。
車を運転する職業は他業界から転職して働く方も多く、こうした方に対する定期的な人間ドックや脳ドックを整備できずにいることが、問題となっているのかもしれません。
脳卒中をわずらうと多くの方が死亡、もしくは介護が必要な状態になってしまいます。
特にくも膜下出血や脳梗塞などは突然に発症することが多く、公共交通機関で働かれていたり、トラックで荷物を配送されている方にとって、発症時に周囲へ及ぼす影響が大きくなることが懸念されています。
運転中の脳卒中が事故につながりやすいわけ
脳卒中の中でもくも膜下出血、脳出血、脳梗塞などはよく知られています。 くも膜下出血は前兆もなく突然発症し、意識障害を来すことがあります。 偶然にも運転中に発症するとコントロールがきかずに、大事故につながると考えられます。
(記事監修医コメント)
知っておきたい脳疾患の基本
脳卒中ってなに?
脳卒中という言葉がありますが、これは脳血管に起きる疾患のことで、医療関係者の中では「脳血管疾患」と呼ばれたりします。
脳は大量の血液を必要とする器官で、動脈が破けたり詰まったりすると、脳細胞に必要な栄養を届けることができなくなります。
脳は1分あたり約800mlの血液を必要とする(※個体差あり)ほど、つねに多量の栄養が要ります。ですから脳に栄養が行き届かないと、私たちの会話能力や運動能力などに影響が与えられます。
この「脳卒中」の中でも、有名なものは「脳梗塞」「くも膜下出血」「脳出血」などがあります。

くも膜下出血に初期症状はある? 突然の頭痛には要注意!
くも膜下出血は、脳出血の1つです。 発症すると死亡する確率が高いのが特徴で、その確率は約50%にも及びます。回復しても後遺症が残る場合が多く、再出血が起こるとさらなる生命の危機に晒されます。この記事では、くも膜下出血に関連するとされる要因や、発症の前触れの可能性がある症状についてお伝えします。
40代から増え始める脳の異変、50代・60代はさらに要注意
若い方の中で多いのが、脳動脈にできた瘤が破裂して起こるくも膜下出血。
ですから、若い方でも無関係ではありません。
しかしながら、やはり脳卒中の数が多くなるのは40代をすぎてから。
50代・60代になると、この疾患になる方が増えてきます。
なぜ年齢が上がれば上がるほど問題が起こりやすくなるかというと、これは長年の生活習慣の乱れで少しずつ体に負荷がかかるためです。
何十年にもわたる少しずつの負荷が、目に見える大きな疾患に変わるのが50代・60代の方なのです。
生活習慣の改善が鍵
生活習慣は、大きく「睡眠」「食事」「運動」にわけることができ、これらを若い頃から意識して整えておくことが、高齢になったときにも脳卒中を起こさないために重要なポイントとなります。
脳ドックをはじめとする検査は自分の生活習慣の歪みを正すきっかけにもなります。
生活習慣を健康に保つことが、脳卒中を遠ざけるもっとも大切な要素になることは理解しておきましょう。
高齢の運転従事者には脳ドックの定期的受診を推奨

運転という行為は自分だけでなく周囲の方にとっても脅威となり得るもの。
定期的に自分の脳の現状を知り、潜在的なリスクがあった場合には生活習慣をしっかり改善することが重要です。
まだ病気と診断される前でも、脳の状態は刻々と変化していきます。
症状が出る前に脳の異変を発見することで、大きな事故が起こるかもしれないリスクを摘み取ることが可能です。
安心して仕事を行うためにも、ぜひ脳ドックの受診を高齢ドライバーの方にはおすすめいたします。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
脳の健康状態を調べてみませんか?
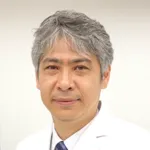
病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。





