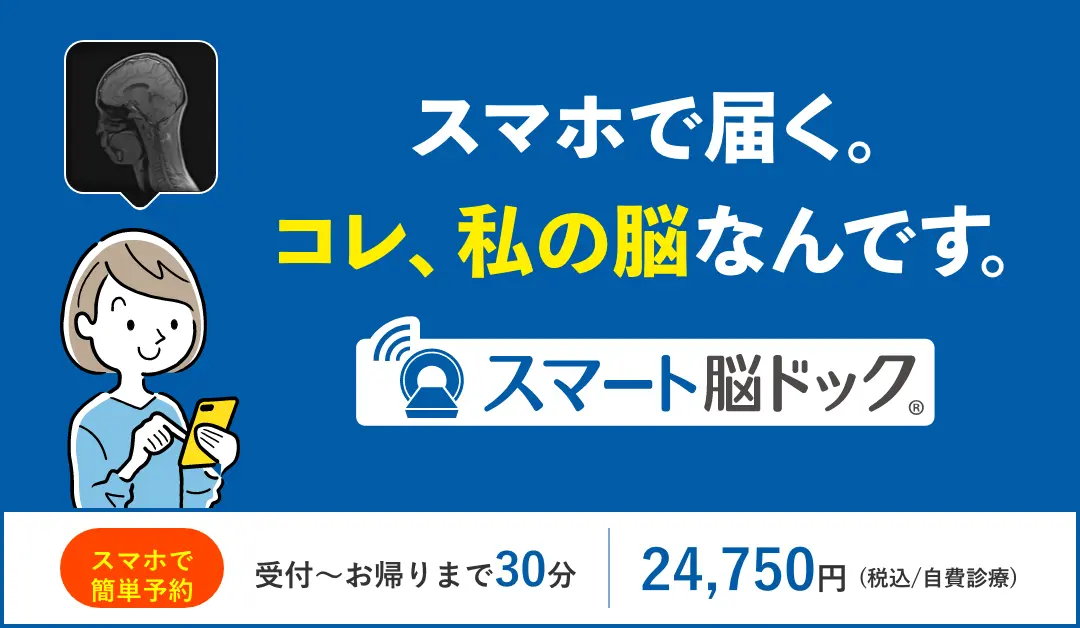うつぶせ寝のすすめ いびきの予防や疲労回復にも!
自律神経を整え、疲労回復や免疫力の向上・睡眠の質を上げるとされる、「うつぶせ寝」の効果や方法を紹介します。体をしっかり休められる自分に合った寝方を見つけてみてはいかがでしょう。※ 人によっては、体に合わない、すっきり起きれないなどの影響が見られる場合がございますので、デメリットも確認の上お試しください。2025/04/28 ( 公開日 : 2023/05/23 )
自律神経はどう整える? 副交感神経を優位にする9つの生活習慣

自律神経とは? 交感神経と副交感神経の役割と仕組み
自律神経は交感神経と副交感神経の2つからなり、自分の意思では動かせず、無意識に働く神経を指します。自律神経には、交感神経と副交感神経がバランスを取り合い、外部からの刺激や体内の変化に反応して内臓や血管などの機能をコントロールする役割があります。
交感神経は、一般的には、身体を動かしたときや緊張したとき、ストレスを感じたときに活発化します。
副交感神経は主にリラックスしているときや眠っているときに優位になります。心拍数や血圧を低下させることにより身体の回復やエネルギーの補給をうながしたり、消化管の働きを活発化させて消化や排せつをスムーズにおこなったりする役割を担っています。
しかし、自律神経が乱れると交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、心身の不調をきたす場合があります。

あなたの自律神経は大丈夫? チェックリストで確認しよう
自律神経が乱れると、以下のような症状がみられる場合があります。
当てはまる項目がないかチェックしてみてください。
- ● 寝つきが悪く、夜中に何度も目が覚めたり、朝早く目が覚めたりする
- ● 疲れや身体のだるさを感じることが多い
- ● 頭痛やめまい、立ちくらみが起こりやすい
- ● 急な胸の苦しさや、息苦しさを感じることがある
- ● 不安やイライラが持続している
- ● ささいなことに神経質になる
- ● 落ち着かずそわそわしてしまう
- ● 動悸や胃もたれ、胸やけが頻繁に起こる
- ● 便秘や下痢が続いている
- ● 手足の冷え、しびれ、慢性的な肩こり、腰痛、耳鳴りがある
- ● 風邪を引きやすく、体調不良が続きやすい
- ● 目が疲れやすい
- ● 食欲不振や体重減少がある
上記のチェックリストで当てはまる項目が多い場合、自律神経が乱れている可能性があります。自律神経が乱れていないか心配な方は、精神科や心療内科の受診をおすすめします。
自律神経が乱れる原因は?
自律神経が乱れる代表的な原因としては、以下のものが挙げられます。
・精神的ストレス
仕事や人間関係の悩み、環境の変化などは交感神経を過剰に刺激し、自律神経のバランスが崩れる場合があります。
・生活習慣の乱れ
不規則な食事や過度な飲酒、喫煙、睡眠不足、運動不足などの生活習慣は、自律神経の働きに悪影響を及ぼす可能性があります。
・ホルモンバランスの乱れ
女性の月経周期、妊娠中、更年期などはホルモンの変動が大きく、自律神経のバランスが崩れやすいです。男性では加齢によるホルモンバランスの変化が自律神経に影響する場合があります。
・季節の変化
季節の変わり目には、気温や気圧の急激な変化などに自律神経が適応しようと過剰に働くことでバランスが乱れやすくなります。
これらの原因に適切に対応することで、自律神経の乱れの予防が期待できるでしょう。

自律神経を整えるために意識するべきポイントとは
自律神経のバランスが崩れる原因には、生活習慣の乱れが関与している場合もあります。以下のポイントを意識すると、自律神経のバランスが整う効果が期待できるでしょう。
バランスのよい食事を心がける

栄養バランスのとれた食事は、自律神経が乱れるリスクの低減につながるとされています。食生活の乱れにより一部の栄養素が不足すると、自律神経の調整に支障が出る可能性があります。一方で、腸内環境の改善はストレスの軽減や心身の安定につながるとされています。食物繊維や発酵食品を食事に取り入れることも効果的です。
適度な運動に取り組む
適度な運動は、副交感神経の働きを高めます。1回30分程度のウォーキングや階段による移動、すきま時間のストレッチや筋トレなどに取り組むとよいでしょう。ただし、負荷が大きすぎる運動は自律神経の乱れにつながる可能性があります。交感神経の働きを過剰に高め、副交感神経の働きが得られにくくなる可能性があるためです。
十分な睡眠を確保する
十分な睡眠は、自律神経を整える効果が期待できます。早く寝ることを心がけ、十分な睡眠時間を確保しましょう。
睡眠の質の低下や睡眠不足は自律神経の乱れにつながるケースもあります。
「眠っているのに疲れが取れない」「日中に眠気を感じる」「集中力が持続しない」などの症状がある場合には、睡眠障害をきたしている可能性もあります。
なかでもいびきがひどいケースでは、睡眠時無呼吸症候群の可能性が考えられます。睡眠時無呼吸症候群では、倦怠感や日中の眠気、高血圧症をはじめとした生活習慣病との関連性が指摘されています。思い当たる点がある方は、一度専門の医療機関を受診することをおすすめします。
禁煙に取り組む
喫煙習慣がある人は禁煙に取り組みましょう。タバコに含まれるニコチンは交感神経を刺激する作用があり、自律神経のバランスを悪化させるリスクが高いためです。自律神経が乱れている状態での喫煙は、血流の停滞によって身体のさらなる冷えや臓器の活動低下にもつながるため、禁煙に取り組むことは重要です。
漢方薬を活用する
自律神経に関する症状には、漢方薬が有効な場合もあります。
半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)は、精神的なストレスによる不安感や不眠などの症状に効果が期待できます。
漢方では、一人ひとりの体質や病態に適した治療が重要なため、同じ症状であっても処方が異なる場合があります。使用を検討している場合は、漢方にくわしい医師に相談することをおすすめします。

副交感神経を優位にする9つの生活習慣
身体の回復やエネルギーの補給などをもたらす副交感神経の作用を高める生活習慣をご紹介します。
いずれもすぐに取り組める内容なので、ぜひ試してみてください。
起きたら15秒間くらい朝日を浴びる

起きたらカーテンを開けて朝日を浴びましょう。朝日を浴びると脳内でセロトニンという心の安定や意欲に関与する物質の分泌がうながされ、自律神経のバランスを整える作用が期待できます。
ストレッチや軽い運動をする

ストレッチや軽い運動を行うことで副交感神経が優位になり、リラックスしやすい状態になります。
具体的な例としては、ウォーキングやヨガなどが挙げられます。
夕食が遅くなる時は、軽めにする

遅い時間帯の夕食は自律神経を活発化させ、睡眠の質が低下する可能性があるため、就寝の約3時間前までに食事を済ませることをおすすめします。
どうしても食事が遅くなる場合は、軽めの食事をとるようにしましょう。
就寝前のパソコンやスマホは控える

就寝前のパソコンやスマホの使用は控えましょう。
液晶から発せられるブルーライトが、メラトニン(睡眠を誘導するホルモン)の分泌を妨げるほか、交感神経を優位にする効果があるためです。
身体がリラックスしづらくなることで、寝つきの悪さや睡眠の質の低下につながると言われています。
寝る1時間前には、パソコンやスマホの使用は控えるとよいでしょう。
ストレスを感じたら、深呼吸をする

深呼吸は副交感神経の働きを高め、心拍数の低下や血圧の安定、リラックスした状態への移行が期待できます。ゆっくりと鼻から息を吸い込み、時間をかけて吐き出す呼吸を意識してみてください。
睡眠時の姿勢を検討する
睡眠時の姿勢が自律神経の状態に関連しているとの指摘があります。横向きやうつ伏せで寝ると安心感が得られ、リラックスできる場合もあります。例えば、睡眠時無呼吸症候群や肥満では、仰向けの状態に比べて気道が確保されるため、睡眠の質の向上につながる可能性があります。
ただし、一般的に、高齢者や乳幼児にとってうつ伏せの姿勢は、睡眠に適していないと言われているため、注意が必要です。また、睡眠時に自律神経に良好な状態をもたらす姿勢には個人差があります。普段と異なる姿勢が自分に合っていないと感じた場合は無理をせず、通常の姿勢で眠るようにしてください。

音楽を聴き、リラックスした時間をつくる

音楽は自律神経に良い影響を与えることが報告されています。ゆったりとしたテンポの音楽は、心拍数や血圧の安定につながるとされています。お気に入りの音楽を聴き、リラックスした時間をつくるとよいでしょう。
カフェインを摂取する時間帯を意識する

カフェインを摂取する場合は、時間帯に注意するとよいでしょう。カフェインは交感神経を活性化させる作用があるためです。遅い時間帯の摂取は睡眠の妨げになる可能性もあるため、夕方以降の摂取は控えるとよいでしょう。
また、カフェインの過剰摂取は心拍数を増加させ、不安感や睡眠障害などの原因となる可能性があります。カフェインの摂取は適度にとどめておきましょう。
日頃からよく笑う

笑うと副交感神経が優位になり、リラックス効果やストレスの軽減が期待できると言われています。
ストレスがたまっている状態で笑うことは難しいかもしれませんが、日頃から笑顔を絶やさない生活を送るとよいでしょう。
まとめ:リラックスタイムを大切に
自律神経の乱れを予防するには、普段の生活習慣の改善に取り組むことが重要です。
体調不良は自律神経の乱れが原因かもしれません。リラックスする時間を意識的につくり、身体をいたわりましょう。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
メディカルチェックスタジオでは
頭痛、動悸・息切れ、
睡眠時無呼吸症候群などの
専門外来を受け付けています。
こちらの記事もおすすめ

知っておきたい脳ドックの補助金・助成金制度 思っていたよりずっと安く受診できるってほんと?

脳ドック受けてみた! 各種メディアさま スマート脳ドック | 体験レポート

心臓ドックって何をするの? 突然死につながりやすい心疾患を予防しましょう!

こわい/こわくない頭痛とは? 脳梗塞は頭痛を感じないってほんと? 知っておきたい頭痛の分類

微小脳出血(CMBs)とは? 将来的な脳梗塞リスクと関係あるの?

認知症にならないためにできることは? 予防の「10か条」も収録

話題のオートミールは健康にいいの? 栄養素や種類についても解説!

血圧管理には減塩が効果的! 1日の目標とすべき塩分「6g」ってどの程度?

筋肉は体にどんな働きをしてるの? 知っておきたい筋肉の7つの働き

健康面でのリスク管理はできていますか? 知久先生にインタビュー

脳の検査に求めることは? 費用(金額)? 検査時間? 受診に至らない理由も掲載

20代社会人の子どもを持つ親は健康面のリスク管理はできている?