尿酸値を下げるにはどうすればいいの? 高尿酸血症が持つリスクとは?
「尿酸値が高い=痛風になる」というイメージが強いと思います。これに関しては間違っていませんが、尿酸値の高さは、ほかにもさまざまな病気につながり、さらには低すぎても病気になる可能性があります。この記事を読むことで、尿酸の数値に異常があったとき、どんな病気を起こす可能性があるのかを知ることができます。痛風はどんな痛み? 高尿酸血症の3つのタイプについても紹介!
 138
138
痛風ってどんな病気?
一般的にいわれる「痛風」は、痛みの症状を指すことが多いですが、痛風による関節炎などでの痛みは「痛風発作」といいます。
痛風は尿酸が蓄積して結晶化することで、関節などに痛みを引き起こす病気です。
「風が吹くだけでも痛い」ことに由来して、痛風という名称がついています。
痛風の症状
痛風発作はある日突然起こり、耐えがたいほどの痛みが2-3日つづきます。
1-2週間すると痛みは落ち着くことが多いですが、落ち着いてもまたあるとき痛みを引き起こすことがあります。
足の親指の付け根でよく起こり、赤く腫れ、痛みを伴います。

治療により短期間で痛みは引きますが、痛みが引いても基準となっている尿酸値を維持することが必要になります。
薬をやめたり放っておくと再発する可能性が高いため、油断してはいけません。
痛風の原因
痛風は血液中の尿酸濃度が高い「高尿酸血症」がおもな原因です。
CMやお酒のパッケージなどで「プリン体」とういう言葉をよく耳にするかと思います。
悪い印象をお持ちの方も多いと思いますが、身体を動かしたり内臓を正常に働かせるために必要なエネルギー源であり、常に体内で産生されています。
食事から取り入れられるプリン体は全体の2割程で、約8割は体内でつくられています。
プリン体が使われたあと、肝臓などで分解されて生まれるものが尿酸です。
血液中にある過剰な尿酸が結晶化して関節に溜まります。
これを白血球が異物と誤って認識し、攻撃して炎症が起こることで、痛風発作が起こります。
尿酸については、こちらの記事もご覧ください。

痛風になりやすい人の特徴
- 血清尿酸値が7.0mg/dLを越える状態が数年間つづいている
- 30~50歳代の男性(女性より圧倒的に男性が多い)
- 尿酸の排泄能力が低い
女性に少ない要因は、女性ホルモンに腎臓から尿酸の排泄を促す働きがあるためです。
尿酸の排泄能力が低く、日頃からビールなどでプリン体を摂りすぎている人は痛風になりやすいといえます。
また肥満や高血圧や高脂血症(LDLコレステロールや中性脂肪が高い)の人は、尿酸が蓄積されやすいため同様に痛風になりやすいです。
痛風の診断方法

視診、触診、問診などの基本的な検査に加えて、血液検査、尿検査、尿酸クリアランス検査、超音波検査をおもに行い診断します。
血液検査で尿酸値、尿検査で尿中尿酸濃度を計測し、尿酸クリアランス検査で痛風のタイプ(原因)を診断します。
また、超音波検査(エコー検査)は痛風と似ている病態や症状を持つ、偽痛風との鑑別にも有効です。
痛風になりやすい高尿酸血症の3つのタイプ
痛風の原因となる「高尿酸血症」では、よく見られる3つのタイプがあります。
それは産生過剰型、排泄低下型、混合型です。
産生過剰型
暴飲暴食によってプリン体の摂取量が増えたり、新陳代謝・エネルギー代謝が増えることで、尿酸が過剰に産生されているタイプです。
このタイプには尿酸生成抑制薬を使います。
約10%が産生過剰型です。
排泄低下型
プリン体の量は増えていませんが、体の外への尿酸排出量が減っている状態です。
3つのタイプの中でもっとも多く、痛風患者全体の約60%がこのタイプといわれています。
こちらの場合、尿酸の排出を促す治療が必要になります。
混合型
産生過剰型と排泄低下型が合わさった状態を、混合型と呼びます。
排泄低下型のつぎに多いタイプで、全体の約25%ほどといわれています。
尿酸の産生が増えているうえ、尿酸の排出も減っている状態で、同様に尿酸を減らす治療を行っていきます。
痛風の治療方法
痛風の治療はまず痛風発作の炎症による痛みを改善し、落ち着いたあとに血液中の尿酸値6未満を維持することを目的にします。
痛風発作が起こっていない場合は尿酸値を下げるために、産生過剰型の患者には尿酸の産生を抑制する薬、尿酸排泄低下型の患者には尿酸の排泄を促す薬を処方し、再発しないよう継続的に治療を行っていきます。
痛風発症時の応急処置(対処法)
・机の上に足を上げる(患部が足の関節の場合)など、患部を高い位置にする
・患部を冷やす(氷を入れた袋やアイスパックにタオルを巻いたものなど)
・患部は安静にし、マッサ-ジなどは行ってはいけない
・あらかじめ医師から痛風発作用に処方された薬があれば使用する
痛風の予防方法
痛風の主な原因は高尿酸血症であるため、尿酸を生んでしまうプリン体の摂取量を抑えることがもっとも有効的です。
「尿酸値が高い」といわれたら、痛風の症状がなくても生活習慣を見直し、尿酸値を下げることが大切です。
この機会に生活習慣を見直し、痛風だけでなく生活習慣病の予防を行いましょう。
食生活を見直す
大前提としてプリン体が多い食品(牛肉や豚肉、レバー、エビ、干物など)の摂取を少なくしましょう。
その上で尿をアルカリ性にする作用があるもの(野菜、海藻、いも類、きのこ類)を取り入れたり、尿酸の排出を促すために水分を一日に2L以上摂ることをおすすめします。
尿酸を下げるための食事については、こちらの記事もご覧ください。
プリン体ってなに? 尿酸値を下げるためのコツもご紹介いたします!
痛風でお困りの方は、プリン体に気をつけないと、と思っているのではないでしょうか。しかしプリン体とは、そもそもどのようなものなのでしょう。なぜビールやレバーなど、プリン体を多く含むものを摂取し続けると足が痛むのでしょうか? 今回の記事では痛風が起こるメカニズムや、尿酸値を下げるためのコツなどをご紹介いたします!
アルコールの摂取量を抑える

上記と重なりますが、プリン体が多いアルコール飲料(ビール、日本酒、ワインなど)を控えましょう。
どうしてもアルコールを飲むならプリン体が少ないもの(焼酎、ウイスキーなど)を少量にしましょう。
適度な運動をする
適度な有酸素運動を生活に取り入れるようにしてください。
代謝の向上により、尿酸の排泄能力が改善したり、肥満の解消で尿酸の蓄積を防ぐことができ、痛風予防につながります。
適度な運動は痛風に限らず、あらゆる病気の予防になるため、少しでも生活に運動を取り入れることを推奨いたします。
ストレスを溜め込まない
ストレスも尿酸値を上昇させるという報告があります。
またストレスが増えると、飲酒量が増えたり過食になったりして、さらに悪循環に陥ってしまうため注意が必要です。
ストレス解消法は自身に合ったものを、ひとつでも見つけておくことが大切です。
ストレスに強くなるためには日頃から十分な睡眠と休養、バランスのとれた食事、適度な運動など規則正しい生活を心がけましょう。
痛風には合併症のリスクも

慢性腎臓病、尿路結石なども、痛風発作と同じ尿酸の結晶によって引き起こされます。
さらに狭心症や心筋梗塞、脳出血、脳梗塞も尿酸値が高いほど起きやすいとされています。
狭心症ってどんな病気? 生活習慣を見直すことと、定期的な検査が予防の鍵
食生活の欧米化と高齢化社会にともない狭心症をはじめとした虚血性心疾患の患者数が増加傾向にあります。狭心症では心臓への血液が減ることで、胸の苦しさや動悸などの症状が感じられる方が多いです。この記事では、狭心症についてわかりやすくまとめ、狭心症にまつわる検査や治療について解説していきます。
心筋梗塞を予防するには何をすべき? 症状や診断方法についても解説します!
心筋梗塞はなぜ起こるのか、どのようにすれば予防ができるのか。もしも心筋梗塞の方を見かけたときには何ができるのか。死因の上位にもくる心筋梗塞について、正しく知って正しい予防を心がけましょう。この記事の中では、心筋梗塞の押さえておきたい基本をご紹介いたします。
脳梗塞の前兆となる症状とは? 急に起こる身体の異変に注意!
脳梗塞はある日突然発症し、その日から身体の自由を奪ってしまう病気です。しかし前兆となる症状も多く報告されており、日常に潜む「脳梗塞の前兆」を見落とさずに検査を受ければ、発症を未然に防ぐ可能が高まります。この記事では、脳梗塞の前兆となる症状や、注視したいポイントについて解説します。
痛風や合併症を予防するには定期的な健康診断などで尿酸値をチェックすることが大切です。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
脳の健康状態を調べてみませんか?
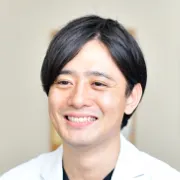
京都府立医科大学卒業後、虎の門病院入職。内科全般を学び、その後がんや慢性疾患を多く扱う消化器内科医に。『健康防衛・健康増進』の重要性を痛感。『患者様の健康増進のために本気で取り組みたい』という強い想いで、愛和クリニック開業。





