血液検査でわかる病気は? 知識が増えれば病気の予防にも役立ちます!
多くの方が経験したことのある尿検査や便検査などを「一般検査」、さまざまな方法によって、血液から異常がないか調べるものを「血液検査」と呼びます。一般検査や血液検査から分かることは非常に多いです。この記事では、主に血液検査で調べる項目と分かる病気などをまとめています。血栓症とは?原因・症状・検査・予防・治療までわかりやすく解説
 2078
2078
血栓症とは?
血栓症とは、血液中でできた血栓(血の塊)が血管を閉塞することで、障害を引き起こす病気のことです。血液が流れなくなると、その先の細胞に栄養が届かなくなるため、細胞が壊死して機能障害が起こります。
ゆえに血栓症は予防をしっかり行いながら、定期的な検査で兆候を発見することが大切です。
血栓症の種類
血栓症は、血栓ができる血管の種類によって、動脈血栓症と静脈血栓症の2つに分けられます。
血栓は血流に乗って移動するので発症する場所は様々ですが、それぞれ血栓のできるメカニズムには特徴があります。
血栓症の原因と引き起こす疾患を解説した後に、メカニズムを簡単に解説します。
動脈血栓症の原因と引き起こす疾患
動脈は心臓から出て酸素や栄養を運んでいる血管のことです。
そこに血栓ができるメカニズムは様々ですが、主に脂質や糖の異常、脱水、不整脈、弁膜症、血管炎、血管内皮細胞の損傷から血小板の活性化などをきっかけにして血栓が起こります。
動脈血栓症が原因となり引き起こす疾患としては
- 脳梗塞
- 心筋梗塞
- 下肢動脈血栓症
などがあります。
動脈血栓症は、生命に危険を及ぼしかねない病気を引き起こします。
生活習慣病と呼ばれる「脂質異常症」や「糖尿病」などは、これらの病気の引き金になるため、日頃から予防することが大切です。
静脈血栓症の原因と引き起こす疾患
血管には2種類あり、動脈と静脈に分かれています。
動脈は心臓から身体の末端に向けて血液を送り、静脈は身体の末端から心臓に向けて血液を送ります。
動脈は心臓のポンプ作用で血液を流しますが、静脈は筋肉を動かす時のポンプ作用の力で血液を流します。
ゆえに身体を長期間動かさないような状態が続くと、身体の筋肉を使わないために静脈の流れが悪くなり、静脈血栓症が起こります。
- 長時間座位による下肢の圧迫
- ギブス固定
- 長期臥床(※ベッドや寝床に長く横になっていること)
- 肥満
などがあります。
妊娠中の女性は長時間横になるため、血液が滞りやすいという危険性があります。
静脈血栓が引き起こす疾患について
- 深部静脈血栓症
- 肺血栓塞栓症
- 腸間膜静脈血栓症
などがあります。
深部静脈血栓症とは、いわゆる「エコノミークラス症候群」のことです。長時間同じ姿勢を取ることで、深部の静脈に血栓ができやすくなります。
また、できた血栓が肺に飛ぶことで「肺血栓塞栓症」が起こります。

▼胸部CT肺ドックについて詳しく知りたい方はこちら
血栓症が起こる原因
血栓症が起こるのは血流、血液、血管のいずれかに異常が起こるためです。
それぞれ単独の原因で血栓症が起こる場合もありますが、基本的に相互に関係して血栓症を引き起こします。
血流異常による血栓症
血流が滞ることで血が固まりやすくなります。この血栓が血流に乗って血管の別の部位に運ばれ、血管を詰まらせてしまうことがあります。これが脳塞栓(脳梗塞)や心筋梗塞が起きる原因です。
血流が停滞する原因は様々ですが、
-
筋肉の力が低下して血液が停滞する
(例:同じ姿勢を続ける、筋力が低下する) -
血液がドロドロになって通りが悪くなる
(例:血管内に腫瘍や脂肪がある)

などがあります。
血液異常による血栓症
血液には血管が傷ついて出血した場合に固めたり、反対に固めたものを溶かしたりするシステムが備わっています。
これらのシステムに異常が起これば、血栓症が起こりかねません。
例えば「固めるシステム」が過剰に働く状態になっていれば、血栓が異常に増え、血栓症を生じさせることになるのです。
血液の凝固を促進する要因として
- 悪性腫瘍
- ピルの服用
- 女性ホルモン剤
などが挙げられるでしょう。
血管異常による血栓症
血管の内側には「血管内皮細胞(内膜)」があります。
血管内皮が傷ついてしまうと、傷ついたところからコレステロールが流れ込み、「プラーク」と呼ばれるお粥のようにじゅくじゅくした塊を形成します。
この塊が壊れると、固めようとするシステムが働いて血栓が作られます。
プラークができると血管は硬くなり、本来の健康な状態の時のように伸び縮みしづらくなります。そのため、血液が流れにくくなり、血栓が作られやすくなります。
血栓症の症状
下肢の静脈に血栓ができた場合、ふくらはぎや太ももに「痛み」「あかみ」「腫れ」「突っ張り」「脚のだるさ」などの症状が生じます。
これらは主に静脈血栓症でみられ、女性に多いとされています。
血栓症といっても、血栓ができる場所や、血栓が運ばれた場所によって生じる障害は異なりますが、心臓や脳に運ばれると生命に危険が及ぶ可能性があります。
ふくらはぎの痛みと血栓症の関連
 ふくらはぎに血栓ができると、その周辺の部位に痛みを生じることがあり、これを深部静脈血栓症といいます。深部静脈血栓症は、足の静脈に血栓ができて、血流が悪くなる病気です。
ふくらはぎに血栓ができると、その周辺の部位に痛みを生じることがあり、これを深部静脈血栓症といいます。深部静脈血栓症は、足の静脈に血栓ができて、血流が悪くなる病気です。
長時間同じ姿勢でいると発症しやすく、飛行機の中で起こる「エコノミークラス症候群」としても知られています。
また、血栓が血流に乗り肺の血管に詰まってしまうと「肺塞栓症」となり、呼吸が苦しくなったり、胸痛みが出たりすることがあります。緊急の対応が必要になることもあるため、そういった兆候がみられた際は、早めに医療機関を受診しましょう。
深部静脈血栓症を予防するには、長時間座りっぱなしにならず、こまめに足を動かすことが大切です。水分をしっかり摂ることも、血流を良くするために重要です。日頃の生活の中で、少し意識するだけでも血栓症のリスクは減らせます。
血栓症の検査方法
「CT」「血液検査」を行ったうえで、血栓症が疑われる場合の確定診断には、超音波検査や血管造影検査が行われます。
肺塞栓が疑われる場合には、「造影CT検査」「肺換気血流シンチグラフィー」が行われることもあります。
まずは問診や視診、触診などでスクリーニング検査を行った後に、上記のような検査で詳しい検査を行っていきます。
Dダイマー検査とは? 血栓症を見つける血液検査
Dダイマー検査は、血栓を見つけるのに役立つ血液検査の1つです。
「Dダイマー」とは、身体の中で血栓ができたり、それが溶けたりした時に出てくる物質です。この検査は、ふくらはぎの静脈に血栓ができる深部静脈血栓症や、肺の血管に詰まってしまう肺塞栓症が疑われる時などに用いられます。
ただし、Dダイマーの数値が高いからといって、必ずしも血栓があるとは限りません。けがや手術のあと、妊娠中や高齢の方でも数値が上がることがあります。そのため、医師はこの検査結果だけで血栓の有無を判断することはせず、症状に応じて超音波検査や造影CTなどの画像検査を追加することもあります。
Dダイマー検査は、採血するために針を刺す時に痛みがありますが、それ以外に身体への負担はほとんどありません。
なお、血液検査でわかる病気については以下の記事でも解説しています。詳細が気になる方はそちらもご覧ください。

血栓症の治療方法
血栓症の治療には薬物療法を第一選択として行うことが多いです。重症化している場合や薬の適応に合わなかった場合には、外科手術やカテーテル治療で血栓を取り除きます。
肺塞栓の場合には、予防的措置としてフィルターを腹部の静脈に入れることがあります。
薬物療法例
| 血栓溶解薬 | 血栓を溶かす作用がある |
|---|---|
| 抗凝固薬 | 血液が固まらないようにする作用がある |
場合によっては、血栓融解薬を用いることで症状が悪化するケースもあるため、血栓の発生箇所や発生原因から治療内容を決定する必要があります。
血栓症の予防方法
動脈血栓症の予防について
動脈血栓症を予防するためには
- 運動習慣をつける
- 生活習慣病を予防する
- 水分補給を行い、脱水を防ぐ
ことなどがあります。これにより血管が硬くなるのを防ぎ、血栓を作り出す原因となる内臓脂肪を減少させることができます。
静脈血栓症の予防について
動脈血栓症を予防するためには
- 長時間同じ姿勢をとり続けることを避ける
- 身体を大きく動かせない(体勢を変えられない)場合、踵上げや足の指や足首を曲げる運動を行う
- 毎日ストレッチをして、筋肉を柔らかくしておく
ことなどがあります。
定期的な検査も血栓症予防の1つ

血栓症予防とともに、最低でも年に1回の定期的な検査で血管の状態の変化をチェックし、血栓症を早期発見することが大切です。
血管の状態や異常は、人間ドックや脳ドックでチェックできます。
血栓症を引き起こす疾患や、血栓症によって引き起こされる疾患、その他の異常を早期発見するためにも両方を定期的に受診してみてはいかがでしょう。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
メディカルチェックスタジオでは
動脈硬化や血管詰まりの
起こりやすさを検査できます。
 まずは空き枠を確認してみる
まずは空き枠を確認してみる
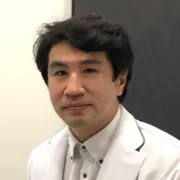
科目 内科・皮膚科・アレルギー科
2023年に千代田区神田で「スキマ時間に通える」をコンセプトとして忙しい方のために空いたスキマ時間、昼休みや仕事終わり、休みの日にも通える内科・皮膚科・アレルギー科のクリニック「クリニックファーストエイド」を開設。






