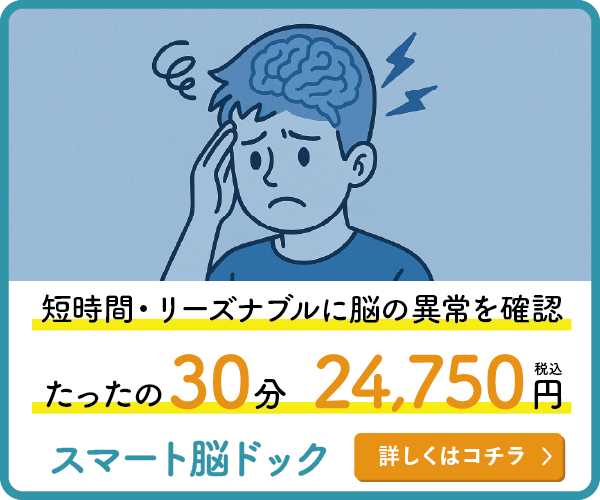隠れ(かくれ)脳梗塞とは? 無症候性の脳梗塞が持つリスクや、日常生活でできる予防をご紹介!
脳梗塞の中には、症状が体に出ない「隠れ脳梗塞」(無症候性脳梗塞)と呼ばれるものがあります。この無症候性の脳梗塞は、果たしてリスクがまったくないものなのでしょうか? この隠れ脳梗塞が持つ、危険性などについて解説いたします。夏に注意! ラクナ梗塞とは? 初期症状、診断に必要な検査、治療法などについて
 1135
1135
ラクナ梗塞とは?

ラクナ梗塞は、脳の太い血管から分岐している一般的に直径0.2~0.3mmほどの細い血管が詰まることで発生します。
詰まると血流が流れなくなり、その先にある脳の組織(神経細胞)が死んでしまうため機能が低下することになります。
しかし梗塞の範囲が小さかったり、脳の高次機能がないところが詰まった場合などは、無症状である場合もあり、これを無症候性脳梗塞(隠れ脳梗塞)と呼びます。
しかし血管が詰まるということは、血管に何らかの損傷があるということ。
無症状であったとしても安心はできません。
実際、ラクナ梗塞は初めて発症した際の治療は一般的に良好ですが、本人も気づかななったり、予防されないことも多いために再発することが知られています。
再発する度に血管や組織は弱くなってしまったり、まひ、嚥下(えんげ)障害、言語障害などを繰り返すことで身体や認知機能も低下する恐れがあります。
無症状の脳梗塞については、こちらの記事もご覧ください。

ラクナ梗塞の症状と早期発見の可能性
ラクナ梗塞は、梗塞を起こした場所によって症状が違うので一概には言えません。
梗塞が起こりやすい場所があるので、代表的な症状をご紹介します。
- 顔を含めた病巣と反対側の半身のまひ(運動障害、感覚障害)
- 話しにくくなる
- しびれ
- 手の細かい動作が難しくなる
などが、よく見られる症状になります。
ちなみにラクナ梗塞では、「意識」を司っている脳の表面に巡る血管ではなく、脳の深部の血管が詰まるため意識障害に至ることは稀です。
もし、ご紹介したような症状が1時間以内に自然に消失すれば「一過性脳虚血発作(TIA)」という病名になります。
しかし、一時的でも血管の詰まりがあったということは、どこかが損傷している可能性があります。放置すると悪化する可能性もあるので、症状があった場合はすぐに医師の診断を受けましょう。
また、無症候性のラクナ梗塞を持っている場合も考えられるので、定期的な血液検査や脳ドックを受診することで早期発見につながります。
その他の脳梗塞
他にも、脳梗塞には「アテローム血栓性脳梗塞」や「心原性脳塞栓症」というものもあります。
アテローム血栓性脳梗塞とは? 原因や検査方法、治療方法についても解説!
アテローム血栓性脳梗塞は太い血管に血栓ができて詰まるもの、心原性脳塞栓症は心臓でできた血栓が詰まるものです。どちらも似たようなメカニズムで起こりますが、アテローム血栓性脳梗塞は動脈硬化、心原性脳塞栓症は心房細動や心筋症などが原因になります。今回は原因や治療方法、必要な検査や予防方法などを詳しく紹介いたします。
ラクナ梗塞発症の原因

ラクナ梗塞は、血管が損傷することで起こる動脈硬化が原因ですが、動脈硬化には三大危険因子と呼ばれるものがあります。
- 高血圧
- 脂質異常症(高脂血症)
- 糖尿病
以上の3つが三大危険因子と呼ばれています。
さらにこれらを悪化させる生活習慣として「喫煙」「過剰な飲酒」「運動不足」「肥満」などがあります。
これらの悪い習慣は、心臓の血管に負担をかけて、心疾患も引き起こす可能性があります。
紹介した3つの中でも、とりわけ原因になっているものは「高血圧」です。
普段から血圧管理を行うことは、ラクナ梗塞だけでなく他の脳卒中の予防にもなります。
血管の損傷は、若い方でも、多少なりとも起こっていますが、修復が効くために症状に表れにくいとされています。
それが悪化し表面化してくるのが、中年期から高齢期にかけてにより多くなるため、発病率が高くなっているのです。
若いから安心とは思わず、早め早めに注意をしていきましょう。
高血圧や、脂質異常症については、こちらの記事もご覧ください。
生活習慣病の原因は? すぐに実践できる5つの改善方法を紹介いたします!
日本人の三大死因であるがんや心血管疾患、脳血管疾患の発症には生活習慣病が関係していることが分かっています。生活習慣病対策としては、自分の生活を見直すことが大切。この記事の中では、生活習慣によって引き起こされる病がどんな病気なのか、また予防や改善方法などについて解説します。
ラクナ梗塞の診断に必要な検査
ほとんどのラクナ梗塞はMRI画像の検査結果で診断できます。
発症早期を発見したい場合は、脳MRI検査で「拡散強調画像」という特殊な撮影方法を用います。
(※MRIには、撮像条件ごとにさまざまな設定があります。ADC、FLAIR、FISPなど。)
CT画像や他の条件で撮像されたMRI画像では、発症6時間以内の脳梗塞を見つけることが難しくなっているためです。
拡散強調画像とFLAIR画像というものを組み合わせて、ラクナ梗塞の中から比較的最近発症したものを区別することも可能です。
近年では、ラクナ梗塞に伴って微小出血が起きている頻度も高いと分かっており、微少出血を見つけるのが得意な「T2スター強調画像」も使われます。
また他の脳卒中と区別をするために、CT画像やMRAという脳血管の検査、頸動脈エコー、心電図などを行うこともあります。
▽以下の記事の中でも撮像条件などについて説明しています
MRI検査ではなぜ大きな音が鳴ってうるさいの? 傾斜磁場ってなに?
MRI検査はなぜ大きな音がするのでしょうか? 記事の中ではMRIで撮像に時間がかかる理由や、撮影中に大きな音が鳴りつづける理由などについて解説しています。
ラクナ梗塞の治療方法
ラクナ梗塞の治療方法として、いちばん大切なのは高血圧の治療で再発を予防すること。
血液の固まりができるのを抑える薬(抗血小板薬や抗凝固薬)の内服や、点滴を行うこともあります。
また、脳細胞が死んでしまうのを防ぐ薬(脳保護薬)が投与されることもあります。
血管が損傷した場合、「血小板」や「凝固因子」などが集まり修復されていきます。
損傷が大きい場合には大きな血栓となりそれ自体が血管を塞栓してしまう、脳血栓塞栓症が発症します。その働きを抑制することで、血栓ができるのを防ぐのが抗血小板薬や抗凝固療法です。
また、梗塞を起こした部分の細胞は数時間で壊死してしまいます。
周辺の細胞は浮腫(むくみ)を起こし、脳を圧排するため麻痺などの症状が出ることがありますが、浮腫が引くと回復する可能性があるため、その細胞を守るために「脳保護療法」を行うことがあります。
他にも、条件付きで可能な治療法があります。
それは血栓溶解療法(t-PA)というものです。できた血栓を溶かす治療法で、発症してから規定の時間以内であれば、この治療が可能になります。
内科的治療を行った後でも、後遺症が残る場合はリハビリを行うことがあります。
夏の脳梗塞にも注意
脳梗塞は冬に多いイメージを持っている方も多くいると思いますが、夏にも多くなることがわかっています。
特に日本人が多いとされるラクナ梗塞とアテローム血栓性脳梗塞は夏に起こりやすいとされており、 理由としては脱水による体内の水分不足です。
気温の上昇により、汗をたくさんかくと、それに見合った量の水分を補給していなければ、体が脱水症状に陥って、血流が悪くなったり、血栓ができやすくなったりします。
暑い夏は就寝中も脱水が起こりやすいとされ、夜間に血圧が下がり、血流が滞って血管が詰まりやすくなります。 飲酒に関しても尿量を増加させ脱水の原因になってしまうので飲み過ぎには注意が必要です。
これらが重なってしまうと夜間に脳梗塞が発症するリスクが高くなってしまいます。
対策として、熱中症の予防と同様に、こまめに水分を十分にとり、無理をせず休みながら活動をすることです。 特に高齢者はのどの渇きを感じにくくなっているので、定期的に水分補給をしてください。
また、夏かぜなどの感染症を起こすと、血液が固まりやすくなり脳梗塞が起こりやすくなるので、夏かぜを防ぐことも脳梗塞の予防対策として重要です。
夏の体調不良については、こちらの記事もご覧ください。
なんとなく体がだるい、食欲がない?!もしかして・・・夏バテ?
本格的な夏の暑さが続き疲れがたまってしまい、最近は体のだるさを感じてないでしょうか。このような夏の不調を感じていましたら夏バテかもしれません。 今回は夏バテの症状や原因、予防に加えて、夏場の脳への影響についても触れておりますのでチェックしてみてください。
定期的な検査でラクナ梗塞を予防しよう

ラクナ梗塞は、ごく軽度で済む場合があります。油断をしてしまい、自己診断で病院に行かない人も少なくありません。
しかし、ご紹介したように放置すると悪化する可能性もあるので、ちょっとした症状でも医師の診断を受けることが大切です。
そして何より怖いのは、発症して治癒したと思っても再発する可能性が高かったり、無症状の場合もあることです。異常を感じる方や危険因子に当てはまる方は特に、定期健診を欠かさずに行いましょう。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
脳の健康状態を調べてみませんか?
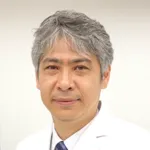
病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。