血圧の正常値とは? 高血圧・低血圧の基準と血圧に関する基礎知識を学びましょう
20歳以上の国民のうちの、3〜4人に1人は高血圧であるといいます。また高血圧を完全に予防できれば、年間での国内の死者数も10万人減らすことができるといわれているため、健康について考える上では非常に重要な指標のひとつです。この記事の中では、血圧のメカニズムや、高血圧の原因についてご紹介いたします。立ち上がったときに頭がぐらっとするのはなぜ? 立ちくらみ、脳貧血とは?
 492
492
立ちくらみは脳貧血?
起床したときや椅子から立ち上がったとき、頭が一瞬ぐらっとする体験をしたことがある方は多いと思います。病気の症状である場合も稀にありますが、日常的によく起こっているようなら脳貧血かもしれません。
脳貧血は起立性低血圧(または起立性調節障害)ともいわれるものです。
これはその名の通り、立ち上がったときに頭にいく血流が保てず、脳貧血状態になることで起こる血圧低下です。
血圧に関しては、こちらの記事もご覧ください。

立ちくらみはなぜ起こる?
ひとの体では起立した場合に、重力によって血液が下半身に貯留して、静脈を経て心臓へ戻る血液量が減少、血圧が低下します。
これを防ぐ目的で体は自然と交感神経を興奮させ、下半身の血管を収縮させ、血圧を保つことによって脳への血液循環を維持します。
しかし体の自律神経機能が低下していると、このメカニズムがうまく働かず、血圧が低下して脳血流が減少するために立ちくらみが現れます。
立ちくらみが多い人は健康リスクあり?
自律神経である交感神経と副交感神経はつねにバランスをとっています。

活動している日中には交感神経が優位になり、心臓の働きを促進して心身を活発にします。
反対に夕方になると次第に副交感神経が優位になり、心臓の働きを緩やかにすることで、体はリラックスします。
立ちくらみはごくたまに起きる程度なら、体が急激に動いたときの反動なので気にする必要はないでしょう。
しかしこの頻度が多く、立ちくらみだけでなく、気持ち悪くなってしゃがみ込んだり、目の前が暗くなって失神する場合には病気が隠れている可能性があるかもしれません。

立ちくらみに隠れている病気
立ちくらみに隠れている病気は、具体的には以下のようなものです。
動脈硬化が関連した疾患(脳・心疾患)
動脈硬化が進むことで、不整脈、心不全、脳梗塞などが起こり、体に立ちくらみとして異変が出ることもあります。
脳に流れこむ血液量は、心拍出量の1/5から1/6ほどの量にもなるといわれていますので、動脈硬化が原因で血液の流れが滞ってしまうと、脳は容易に血液が足りない状態に陥ってしまうのです。
動脈硬化の詳細は、こちらの記事もご覧ください。
動脈硬化にはどんな種類がある? アテローム(粥状)、中膜、細動脈硬化について解説!
動脈硬化は、血管が硬くなってしまった状態のことです。正常な血管はしなやかで、流れる血液の量が多いと伸びたり広がったりすることができます。動脈硬化は加齢でも起こりますが、ほかの原因でも起こります。この記事を読むことで、動脈硬化の原因、メカニズム、診断・予防方法などを学べます。
糖尿病神経障害
糖尿病の合併症で、発症の頻度が高いとされているのが神経障害です。
内臓の働きを調整する自律神経が障害されてしまうと、胃もたれ、便秘、下痢などと共に、立ちくらみが起こることがあります。
また糖尿病神経障害では足先に症状がでやすいことも知られており、以下のような症状がでている場合には早めに病院へ行く必要があります。

・足や足の指がほてる、もしくは冷たく感じる
・足に虫が這っている、もしくは紙を貼ったような感覚がある
・安静時や睡眠中に足が攣る
・足の裏や指先が痺れる
・まるで砂利のうえを歩いているような感覚がする など
糖尿病の詳細は、こちらの記事もご覧ください。
糖尿病とは? 1型と2型の違いや、症状、合併症などについて解説します!
糖尿病は生活習慣病のひとつです。初期段階では自覚症状がないことも多く、いつの間にか糖尿病が進行していたということもあります。糖尿病はほかの病気を引き起こす原因にもなるため、この記事で糖尿病について学び、日頃から糖尿病の予防をしていきましょう。
熱中症

熱中症でも、めまいや立ちくらみなどはよくみられます。
筋肉は体の中で水分を蓄える役割をしていますが、高齢者は筋肉量が減っています。
それゆえに若い偏り熱中症を起こしやすくなります。
また夏場に多くニュースになる熱中症ですが、冬場でも厚着をして部屋を暖かくしていると、体からは水分が不足した状態になります。
喉の渇きを感じるまえに、水分補給を行うように心がけましょう。
パーキンソン病(高齢者の場合)
高齢者の100人に1人が発症するといわれるパーキンソン病は、動作が遅くなったり、手足が小刻みに震えたり、筋肉が固くなるという症状があらわれます。
脳貧血が起き、立ちくらみがすることもあります。
パーキンソン病では、発症の初期からみられる症状として以下のものがありますので、こうした異変がでているかどうかにも注意しましょう。
・動きが素早くできない
・歩くときに足がでにくい(すくみ足)
・話し方に抑揚がなくなり、声が小さくなる
・書く文字が小さくなる など
薬の副作用で起こる立ちくらみ
降圧剤を服用している方は、薬が原因で立ちくらみを起こしやすくなります。

特に薬の服用を始めたときに起こりやすいといわれています。
頻繁に立ちくらみやめまいが起こるときには、薬の量を調整してもらう必要があります。
立ちくらみを予防するには?
自律神経である交感神経と副交感神経が乱れていると、立ちくらみは多く起こります。
すぐにできる予防策としては、以下のようなものがあります。
- 規則正しい生活リズムを作って、自律神経のバランスを整える
- なるべく日常の中で運動して、新陳代謝が落ちないようにする
- 起床時は横になっている状態から急に起き上がらず、ゆっくりとした動作で起きる
加齢とともに代謝が落ち、不規則な生活で自律神経のバランスが悪くなると、立ちくらみなどの症状が現れます。
現代はさまざまな娯楽商品やコンテンツがあり、食事面でも砂糖や塩が多すぎるお菓子、脂肪分が多い外食などに取り囲まれています。
自分の生活習慣を乱すものには、中毒性があることを理解して、少しずつそのようなものと距離を取ることで体は次第に変化します。
夜更かししない、ジャンクフードを食べる回数制限をもうける、なるべく階段で昇り降りするなど、日常のすこしずつの変化が立ちくらみ予防になりますので、ぜひ今日から生活に変化をつけてみてはいかがでしょう。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
脳の健康状態を調べてみませんか?
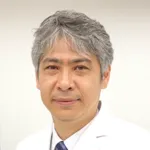
病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。





