CTとMRIの違いとは? 発見できる疾患などそれぞれの特徴を解説
画像検査といえば、多くの方になじみが深いレントゲン検査がまず挙げられます。レントゲンの他にも体内の状態を見ることができる画像検査としては超音波検査、CT、MRI、核医学検査などがありますが、それぞれ特性が異なります。この記事ではCT検査とMRI検査に焦点をあて、それぞれの特徴を解説します。狭心症ってどんな病気? 生活習慣を見直すことと、定期的な検査が予防の鍵
 306
306
狭心症とは?

狭心症とは、心臓に栄養を送っている「冠動脈」の血流が悪くなることが原因で起こる病気です。冠動脈は心臓の筋肉に酸素と栄養を供給しているため、需要と供給のバランスが崩れると胸が痛くなったり、息切れや動悸などを感じるようになります。
狭心症の主な原因は動脈硬化です。血管のいちばん内側の膜が傷つき、コレステロールなどが入り込むことでプラークが蓄積されていきます。
これにより血管が狭くなり、詰まりやすくなった状態になります。
狭心症の種類と症状
狭心症の主な症状は胸の痛み、圧迫感になります。これらに加えて息苦しさや動悸などを感じる場合もあります。 狭心症にはいくつか種類があり、それぞれ病態や症状が異なっているためご紹介します。
労作性狭心症
労作性狭心症とは、歩行や階段などの動作時に息苦しさなどの症状が表れる狭心症のことです。ほかにも、胸の締め付けられている感じや圧迫感があります。
しばらく安静にすると、血液が流れていくため症状が治まる、といった特徴があります。
冠れん縮性狭心症
冠れん縮性狭心症とは、何らかの原因で冠動脈がけいれんするように収縮して、血管内が一時的に狭くなり、血液が流れにくくなる狭心症です。
就寝中や安静時に起こることが多いです。
冠れん縮性狭心症は、心筋梗塞の発症要因にもなるため注意が必要になります。
安定狭心症
血管内で、傷ついた膜の中に入り込んだコレステロールは膜で覆われています。これをプラークといいます。そのプラークが安定してしている(膜が破れそうになってない)状態を、安定狭心症と呼びます。
症状の程度や持続時間などが毎回ほぼ一定で、大きな変化が少ない狭心症です。
しかし血管内腔は狭くなっているため、動作時に胸痛や息苦しさなどの症状が出現します。
不安定狭心症
不安定狭心症とはプラークが破綻してしまい、血中に露出すると「血栓」が形成され、血流を妨げている状態のことです。
プラークの上に血栓ができるため、より血管内腔は狭くなります。徐々に悪化し、安静時にも症状が出現することがあります。
血栓の量が多くて運が悪いと、完全に詰まってしまう「心筋梗塞」へ移行するリスクがあります。
狭心症の診断方法
狭心症は基本的な血圧測定や触診、聴診に加えて詳しく状態を把握するために、心電図検査や心エコー検査などのさまざまな検査を行います。
次にその代表的な検査について解説します。
心電図検査

心臓は電気刺激によって心臓を動かしています。心臓の各部位から伝わる電気信号を、波形に記録したものが心電図です。
心電図に現れる波は、各部位の電気信号の伝わり方や状態を把握することができます。
狭心症がある場合、波の異常が見られ、正常な心電図とは異なる波形(ST変化)になります。
心エコー検査
心エコー検査(心臓超音波検査)とは、超音波を使って心臓の状態を見る検査です。超音波を発して、返ってきた波を分析して画像化します。
心エコーによって心臓の大きさや厚み、弁の状態といった形態、ポンプ機能の状態を把握できるようになっています。
虚血が強いと心臓の壁運動が低下するため、無症状であっても血管の狭窄具合などを知ることが可能です。
運動負荷試験

運動負荷試験(トレッドミル検査)とは、ベルト上を歩いて心臓に負荷をかけ、虚血状態を誘発し、心電図でモニタリングする検査のことです。
あらかじめ年齢によって算出された目標心拍数を目安に行います。
条件として、安静時に心電図が正常な患者に行うこととなっています。症状が強い方、血管内の状態が不安定でリスクのある方、重症者には行いません。
心筋シンチグラフィ
心筋シンチグラフィとは、「放射性同位元素」と呼ばれる製剤を投与して、それらが心臓周辺に集まったところをガンマカメラで体外から撮影する検査です。
放射性同位元素には放射線が含まれますが、X線検査やCT検査で受ける被ばく線量と同程度で健康への影響はありません。
冠動脈3D-CT
冠動脈3D-CT検査とは、心臓CT検査とも言われ、おもに心臓の血管(冠動脈)を診る検査です。
冠動脈は拍動とともに動いているため、通常のCTでの撮像方では長らく描出ができませんでした。
しかし医療機器が進歩したため、現在ではCTによって描出ができるようになっています。
カテーテルによる検査よりも、体にかかる負担を軽減できるのが、大きな特徴であるといえるでしょう。

冠動脈造影検査
冠動脈造影検査とは、手や足の動脈から「カテーテル」と呼ばれる細い管と造影剤を投与し、血管の狭窄の有無を調べる検査です。
造影剤を使用するため、造影剤アレルギーがある場合この検査はできません。異常が見つかった場合そのままカテーテル治療に進むのが一般的となっています。
狭心症の治療方法
狭心症の治療は、血管内腔がこれ以上狭くならないように「薬物療法」を行ったのち、血管内の血液の流れを開通するための手術を行います。
代表的なものをご紹介していこうと思います。
薬物療法
狭心症の薬物治療は、
・抗狭心症薬
・抗血小板薬
・スタチン
などで狭心症の予防および改善を目的に行います。
抗狭心症薬では血管にある筋肉の収縮を抑制することで、血管内腔を保つ効果があります。アスピリンは血管内で血が出たときに固めようとする「血小板」の働きを抑制します。
スタチンは血管内のコレステロールの蓄積を減らしてくれるものになります。
血管内治療法
狭心症の外科的治療は「カテーテル治療」が主流です。
中でも金属製のステントを狭い場所に留置して、血管を拡張する「ステント留置術」が主流になっています。
こちらは物理的に血管内腔を広げることで、血液の流れを改善します。
状態が良ければ、数日程度で日常生活への復帰が可能です。
外科的治療法(冠動脈バイパス術)
バイパス手術は、狭くなった冠動脈を迂回する形で、新しい血液の通り道を作る手術です。バイパスに使う血管は、患者さん自身の体の動脈(おもに胸の裏側の動脈、手の動脈、胃の動脈など)を組み合わせて使用されます。
髪の毛の半分ほどの太さの系で冠動脈に対して縫い合わせを行い、新しい血液の通り道を作ることで、心臓に流れる血液の量を増やします。
狭心症の予防方法

狭心症の原因となっている「動脈硬化」を予防しなければいけません。
動脈硬化の危険因子として「糖尿病」「高血圧」「高脂血症」「喫煙習慣」に加え、「精神的ストレス」も大きく影響しています。狭心症は心筋梗塞に移行する可能性があるため、しっかり対策を立てましょう。
生活習慣の改善
「糖尿病」「高血圧」「高脂血症」を防ぐためには適度な運動、体重管理、禁煙はもちろん、塩分を控えた食生活が大切です。
特にウォーキングなどの有酸素運動は血流をよくしたり、血管をしなやかにする効果があります。
また、ストレスが続くと血圧が高くなるだけではなく、暴飲暴食によって肥満や糖尿病の原因にもなります。体をリラックスさせることを心掛けて少しずつストレスを解消していきましょう。
定期的に検診を受ける
狭心症の症状を放置していると、心筋梗塞などのリスクが高まり非常に危険です。
定期健診を受けることで、狭心症をはじめとする心疾患の早期発見ができ、完治や予防につながります。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
肺・心臓・血管の状態を
調べてみませんか?
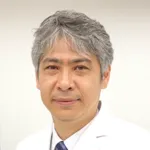
病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。





