立ち上がったときに頭がぐらっとするのはなぜ? 立ちくらみ、脳貧血とは?
長く椅子に座っていたあとで立ち上がると、ぐらぐらと頭が揺れる感覚になることはないでしょうか。このような立ちくらみはなぜ起こるのでしょう? もし頻繁にこうした立ちくらみがある場合には、病気が隠れている可能性があります。今回の記事の中では、病気の可能性があるのかなど、立ちくらみに隠れる危険について解説します。花粉症でなぜ頭痛が起きるの? 副鼻腔炎、脳貧血との関係について
 164
164
花粉症になると頭痛が起きる?
花粉症は、季節性のアレルギー性疾患の1つであり、花粉によりアレルギーを発症している状態です。日本では、花粉症の主な原因であるスギやヒノキの花粉が飛散する春に発症のピークを迎えます。特にスギによる花粉症を患っている人は多く、厚生労働省の調査結果によると、日本人の3人に1人が発症しています(厚生労働省健康局がん・疾病対策課「花粉症対策」)。
花粉症の代表的な症状には、鼻の症状(鼻水や鼻づまり、くしゃみなど)や目の症状(かゆみや充血など)、皮膚の炎症などが挙げられますが、頭痛を合併する場合もあります。
頭痛と花粉症にはどのような関係性があるのか、みていきましょう。
花粉症で頭痛が起きる原因は?
花粉症による頭痛の原因としては、主に以下の理由が考えられます。
- 副鼻腔炎(蓄膿症)
- 鼻づまりによる脳貧血(脳の血流低下)
- マスクの着用
1つずつ確認していきます。
副鼻腔炎(蓄膿症)
副鼻腔炎(ふくびくうえん)は、花粉症によって頭痛をきたす原因の1つです。副鼻腔炎では、副鼻腔(鼻の周りにある骨に囲まれた空洞)内の粘膜への細菌侵入などをきたし、炎症が起こります。

副鼻腔炎が悪化して、鼻の周りや三叉神経(顔面や鼻の中などの刺激に反応する神経)が刺激されると、頭痛を発症すると考えられています。
花粉症と副鼻腔炎を合併したケースでは、頭痛や鼻詰まりなどの症状により不眠症状をきたす場合もあります。花粉症を患っている方で頭痛や咳などがある場合は、できるだけ早めに医師に相談しましょう。
鼻づまりによる脳貧血(脳の血流低下)
鼻づまりによる脳の血流不足も頭痛の原因となる可能性があります。花粉症により鼻づまりになると、鼻呼吸がうまくできず、脳の血流不足により、酸素供給の低下をきたす場合があります。酸素の不足により脳の血管が拡張すると、三叉神経が刺激を受けて頭痛が起こるとされています。
🧑⚕️こちらの記事もおすすめ🧑⚕️

マスクの着用
花粉症対策のために着用したマスクが頭痛の原因となる可能性があります。
マスクによる頭痛の主な原因としては、脱水やマスクのひもによる耳への刺激などが挙げられます。
マスクをつけていると喉の渇きを感じにくく、水分補給が減り、脱水症状が起きやすくなります。脱水が進行すると、頭部における血液循環の悪化や酸素量の不足につながり、脳の血管拡張により神経に刺激が加わり、頭痛が生じる場合もあります。
マスクのひもにより耳の周辺が引っ張られると、神経が刺激されて頭痛が引き起こされるケースもあります。
また、N95などの通気性の極めて低いマスクによって空気を取り込みにくい状態になると、血中酸素濃度が低下し、脳の血管拡張につながり、頭痛が起きやすくなるという指摘もあります。
花粉症で起きる頭痛の解消法は?

花粉症による頭痛の主な解消法は、以下のとおりです。
- アレルギー反応を抑える
- 副鼻腔炎の症状を抑える
- マスクの着用を可能な限り減らす
それぞれ確認しておきましょう。
アレルギー反応を抑える
花粉症による頭痛を解消するには、アレルギー反応の抑制が有効とされています。アレルギー反応とは、身体の免疫が特定の物質に過剰反応を起こしている状態です。花粉をはじめとしたアレルギー物質(アレルゲン)が身体の中に侵入すると、体内で抗体がつくられます。再びアレルギー物質が体内に侵入すると、ヒスタミンなどの物質が分泌されて花粉を体外へ排出しようとします。ただし、ヒスタミンには血管を拡張させる作用があるので、頭痛をきたす場合があります。抗ヒスタミン薬は花粉症の治療薬の1つであり、ヒスタミンの作用を妨げ、鼻水やくしゃみなどの症状を緩和するとともに血管拡張を抑えるので、頭痛の解消が期待できるでしょう。
副鼻腔炎の症状を抑える
副鼻腔炎の悪化予防には、アレルギー症状の抑制や鼻づまりの改善、溜まった膿の排出が重要です。
副鼻腔炎の治療では、通常、抗菌薬による薬物治療が選択されます。ただし、不適切な治療薬の選択は病状の悪化につながる場合もあります。副鼻腔炎が疑われる場合は放置せず、耳鼻咽喉科を受診しましょう。
投薬治療で効果が得られにくい場合や副鼻腔炎を繰り返す場合には、手術が必要になるケースもあります。
マスクの着用を可能な限り減らす
マスクの着用は頭痛の原因となる場合があります。花粉症予防のために外出時におけるマスクの着用は重要ですが、頭痛の予防としては、マスクの着用時間を可能な限り減らすことが有効です。場所やタイミングを考慮して、マスクを外すように意識してみてください。
花粉症が引き起こすめまいとは
花粉症による副鼻腔炎では、頭痛とめまいが併発する場合があります。めまいの症状には平衡感覚の乱れが関与し、鼻づまりや頭痛、ストレスなどにより引き起こされる場合があると考えられています。
花粉症による頭痛の改善が期待できる薬剤とは
花粉症の頭痛に効く主な薬剤は、以下のとおりです。
- 抗ヒスタミン薬
- 鎮痛薬
- 漢方薬
1つずつ確認していきましょう。
・抗ヒスタミン薬
抗ヒスタミン薬は、アレルギー症状の抑制が期待できる薬剤であり、第一世代抗ヒスタミン薬と第二世代抗ヒスタミン薬に分けられます。一般的には、第二世代は第一世代に比べて眠気や副作用があらわれにくいですが、日常的に車の運転をはじめとした危険をともなう作業をする方は、事前に医師や薬剤師に相談することをおすすめします。
・鎮痛薬
鎮痛剤の使用では、頭痛の症状緩和が期待できます。花粉症が頭痛の原因であれば、頭痛の原因となる花粉症の治療に合わせて鎮痛剤などによる頭痛の解消がおこなわれます。ただし、鎮痛剤の使用だけでは根本的な治療にはならないため、注意が必要です。
・漢方薬
花粉症による頭痛には漢方薬の使用も有効です。葛根湯加川芎辛夷(かっこんとうかせんきゅうしんい)は、鼻水や鼻づまりなどの改善に効果があります。副鼻腔炎の改善による頭痛の緩和も期待できるでしょう。
漢方薬は同じ症状でもその人の体質や症状などによって処方が異なります。漢方に詳しい医師に相談して、自らに適した処方を受けることをおすすめします。
妊娠中または授乳中の女性における薬剤の使用は、胎児や乳幼児の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
妊娠中や授乳中の女性は、薬剤を使用してよいか、医師にあらかじめ確認しておきましょう。
花粉症による頭痛は何科に行くべき?
鼻づまりや鼻水などの花粉症の症状があらわれてから頭痛が起きた場合は、副鼻腔炎の可能性があるため、耳鼻咽喉科を受診するとよいでしょう。
頭痛の原因として花粉症との関連性が考えにくい場合や、発熱や倦怠感、脱力感など頭痛以外の全身症状がある場合は、花粉症以外の感染症の可能性が考えられるため、内科の受診をおすすめします。
子どもの場合は、小児科を受診するとよいでしょう。子どもは症状をうまく伝えられない場合が珍しくなく、頭痛が重い病気のサインである可能性もあるためです。
また、重い頭痛や季節性がなく長期的に続く頭痛の場合は、偏頭痛や緊張性頭痛などの可能性があるため、神経内科の受診も検討してください。
まとめ:花粉症による頭痛には早めの受診を
花粉症による頭痛の原因には、副鼻腔炎や鼻づまりによる酸素不足などが考えられます。頭痛の根本的な治療には、花粉症の治療が重要です。市販薬による症状改善がみられない場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
脳の健康状態を調べてみませんか?
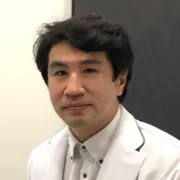
科目 内科・皮膚科・アレルギー科
2023年に千代田区神田で「スキマ時間に通える」をコンセプトとして忙しい方のために空いたスキマ時間、昼休みや仕事終わり、休みの日にも通える内科・皮膚科・アレルギー科のクリニック「クリニックファーストエイド」を開設。




