血圧の正常値とは? 高血圧・低血圧の基準と血圧に関する基礎知識を学びましょう
20歳以上の国民のうちの、3〜4人に1人は高血圧であるといいます。また高血圧を完全に予防できれば、年間での国内の死者数も10万人減らすことができるといわれているため、健康について考える上では非常に重要な指標のひとつです。この記事の中では、血圧のメカニズムや、高血圧の原因についてご紹介いたします。動脈硬化にはどんな種類がある? アテローム(粥状)、中膜、細動脈硬化について解説!
 66
66
動脈硬化の種類とメカニズム
動脈硬化は起こる場所やメカニズムによって、いくつか種類があります。
動脈硬化のメカニズムを知っておき、動脈硬化予防につなげましょう。
アテローム(粥状)硬化
動脈の構造として、内側から内膜、中膜、外膜があります。
内膜が傷つくと、そこからコレステロールが入り込み、プラークと呼ばれる構造ができます。
それにより血管が硬くなったものが「アテローム硬化」です。
プラークが進行して大きくなると、いっそう血管内腔を狭くして血管も硬くなるのですが、狭く硬くなると血管はさらに傷つきやすくなって悪循環が生み出されます。
始めのうちは体に症状がありませんが、徐々に悪化していきます。
これらは比較的太い動脈に起こることが特徴です。
中膜硬化(メンケベルグ型動脈硬化)
動脈の中膜にカルシウムがたまり、石灰化して血管が硬くなったものが「中膜硬化」です。
動脈の中膜に平滑筋(へいかつきん)という筋肉が多く含まれる動脈を筋性動脈と呼びますが、その筋性動脈に対して起こりやすいとされています。
具体的な筋性動脈の例として、上下肢の動脈、頸動脈、腎動脈があげられます。
細動脈硬化
「細動脈硬化」は脳や腎臓の中などの細い動脈が動脈硬化することです。
細動脈も筋性動脈に分類されて、毛細血管に送る血液量を調節する役割を持っています。
高血圧や加齢などで動脈硬化を起こしやすいです。
動脈硬化の原因となる生活習慣病
生活習慣によって動脈硬化が起こりやすくなる場合があります。

・喫煙
・肥満
・ストレス
・運動不足
・過度の飲酒
・睡眠不足
以上の生活習慣を続けることで起こる生活習慣病は、動脈硬化を起こすリスクを高めます。
高血圧
高血圧になると血管へ過剰な圧力がかかることになり、血管の「ずり応力」が動脈硬化を進行させてしまいます。

脂質異常症
脂質異常症は、悪玉コレステロールや中性脂肪が増加し、善玉コレステロールが減っている状態を言います。
脂質異常症になると、血液に流れる脂肪やコレステロールが増え、血管が傷つきやすくなります。それによりプラークができ、動脈硬化が進行するのです。
糖尿病
食べ物から摂取したり体内で作られた糖は、「インスリン」によって筋肉や脂肪組織、肝臓に取り込まれます。糖尿病はこのインスリンの作用や分泌が減り、血液に糖が増えている状態です。
高血圧と同様に、高血糖が血管の内膜を傷つけたり、酸化ストレスがコレステロールを超悪玉にしやすくなり、プラークを作り出すきっかけとなります。
動脈硬化によって引き起こされる病気や合併症
動脈硬化は病変か進行するまでは無症状の場合が多いです。
症状が出る頃には重篤な病気の発症の要因になりますので注意が必要です。
狭心症・心筋梗塞
狭心症や心筋梗塞は、プラークが血管内にできて血液の通り道を狭くしたり完全に塞ぐことで起こるものです。
とくに心筋梗塞ではプラークが破綻して血栓(血の塊)ができることで血管を塞ぎ、突然の心筋梗塞が起こります。
狭心症は心筋梗塞に移行することもあるため、できるかぎり早い対処が必要です。
狭心症ってどんな病気? 生活習慣を見直すことと、定期的な検査が予防の鍵
食生活の欧米化と高齢化社会にともない狭心症をはじめとした虚血性心疾患の患者数が増加傾向にあります。狭心症では心臓への血液が減ることで、胸の苦しさや動悸などの症状が感じられる方が多いです。この記事では、狭心症についてわかりやすくまとめ、狭心症にまつわる検査や治療について解説していきます。
脳卒中
脳卒中は脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、一過性脳虚血発作の総称になります。
脳出血は壊れやすくなった血管が血流に耐えられなくなり、破裂することで出血が起きます。
また脳梗塞はいくつか原因はありますが、血栓が詰まり血液の流れが滞ることでその先の細胞が壊死して障害を起こします。
脳卒中の種類や病気についてもっと知りたい方は、こちらの記事でも紹介しています。
脳卒中の初期症状(FAST)とは?
脳卒中の初期症状としては、FAST(ファスト)という言葉を覚えておきましょう。これらの症状らしきものが出た際には、些細なことのように思えても病院にすぐ向かいましょう。
動脈硬化の危険因子
動脈の危険因子に脂質異常症があります。
異常と診断される数値
LDLコレステロール…
140mg/dl以上の場合 → 高LDLコレステロール血症
120~139㎎/dlの場合 → 境界域高LDLコレステロール血症
HDLコレステロール …
40mg/dl未満の場合 → 低HDLコレステロール血症
総コレステロール …
200~259㎎/dlの場合 → 要注意
260異常の場合 → 異常値
| 脂質の目標値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 治療方針 | カテゴリー | LDL | HDL | 中性脂肪 |
| 一次予防 | カテゴリーⅠ (低いリスク) |
<160 | ≧40 | ≧50 |
| カテゴリーⅡ (中程度のリスク) |
<140 | |||
| カテゴリーⅢ (高いリスク) |
<120 | |||
| 二次予防 | 冠動脈疾患の既往 | <100 | ||
脂質異常症の治療方法
数値と症状に応じてカテゴリーⅠ~Ⅲでは「一次予防」として生活習慣の改善を行ったあと、 薬物療法の適応を考えます。
冠動脈疾患の既往がある場合では、「二次予防」として生活習慣の改善とともに薬物治療を考えます。そもそも「一次予防」とは病気の発生を防ぐことで、「二次予防」は病気がこれ以上重篤にならないようにすることをいいます。
生活習慣の改善するべき例として
・食べ過ぎ
・運動不足
・喫煙
・過度な飲酒
・睡眠不足
があげられます。
薬物療法の例として
・血液中のLDLコレステロールを減らす作用
スタチン、エゼチミブ
・中性脂肪を減らす作用
フィブラート系薬、EPA製剤
などがあります。
知っておきたい超悪玉コレステロール(sd-LDL)
コレステロールは血液中に含まれる脂質のことですが、
HDL(善玉;余分なコレステロールを肝臓に運ぶ)と、LDL(悪玉;肝臓から血管にコレステロールを運ぶ)はよく知られています。
善玉も悪玉も必要なものですが、食生活の乱れなどによってLDLコレステロールの方が増えてしまいがちなため、LDLが悪玉といわれています。
この悪玉コレステロールが血管壁の中に溜まると、動脈は硬化していきます。
とくに注意が必要なsd-LDLとは?
悪玉の中でも、小型の超悪玉(small dense LDL)は血管の中に滞在している時間が長く、血管内皮から入り込んで酸化しやすいです。
この酸化した超悪玉が有毒化して、血管壁にはよりプラークが作られやすくなります。

動脈硬化の予防方法
予防方法は、生活習慣の改善が第一となります。
- 禁煙
- 減酒
- バランスの良い食事
- 甘いものや揚げ物を控える
- 適度な運動
- 十分な睡眠をとる
上記のような、一般的に「健康にいい」とされる生活を送ることが大切です。
反対のことをすると動脈硬化を助長するため、注意しましょう。
動脈硬化が心配な人は定期的に検診を受けよう

定期的な検査で血管の状態の変化を知っておくことも、動脈硬化が進行するのを予防するために必要です。
血管の状態は、超音波検査や脳MRA検査でチェックできますが、動脈硬化によって引き起こされる病気やその他の異常を早期発見するためにも、両方とも定期的に検査すると安心です。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
超悪玉コレステロールを
調べてみませんか?
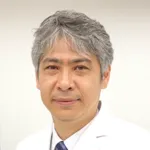
病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。


