脂肪肝はどうやって治せばいいの? 血液検査だと発見できない場合もあるってほんと!?
アルコールによる肝機能障害はよく知られていますが、お酒をあまり飲んでいない方でも、脂肪肝になる方が増えています。脂肪肝は自覚症状がほぼないため、健康診断で指摘されても気にしないことが多いです。しかし脂肪肝は放置しておくと脂肪肝炎になってしまい、その後は肝硬変や肝がんになってしまう方もいます。肌や白目が黄色い…これって病気?「黄疸」の基礎知識と受診の目安
 88
88
黄疸とは? 肌や白目が黄色くなる理由
黄疸(おうだん)とは、血液中のビリルビンという物質が増えて、肌や白目が黄色くなる状態を指します。ビリルビンは古くなった赤血球が分解される際に生じる物質で、通常は肝臓で処理され、胆汁の成分として体外へ排出されます。しかし、何らかの原因でビリルビンが処理されないと、血液中にビリルビンが蓄積し、黄疸が発生します。
具体的には、以下の原因により黄疸が発生します。
- 肝機能の低下 :肝炎、肝硬変など
- 胆道系の通過障害:胆石、腫瘍など
新生児の場合、主に以下のような原因で黄疸が起こります。
- 赤血球がたくさん壊れ、大量のビリルビンが発生する
- 肝機能が未熟で、ビリルビンをうまく処理、排出できない
新生児の黄疸は一時的で、特別な治療をしなくても自然に改善することがほとんどです。しかし、成人の場合は黄疸の原因が多岐にわたるため、症状が見られたら消化器内科を受診しましょう。
黄疸の主な症状|見た目と体調の変化
黄疸に伴う主な症状は以下の通りです。
| 肌や白目が黄色くなる | 黄疸の最も顕著な兆候 |
|---|---|
| 尿の色が変わる | 尿が濃い茶褐色になる |
| 便の色が変わる | 便が非常に白かったり、薄い黄色になったりする |
| だるさが出る | 全身の倦怠感を感じる |
| 食欲不振になる | 食欲が減少する |
| かゆみが出る | 身体中がかゆくなる |

これらの症状、特に複数の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診することを推奨します。
黄疸の症状①肌や白目が黄色くなる
黄疸の最も特徴的な症状が、肌や白目の黄ばみです。特に白目(眼球結膜)の黄染は自覚しやすく、周囲の人から指摘されることも少なくありません。
日光の下ではより目立ち、顔や手のひらなどで確認されます。初期には一部に限られることもありますが、進行すると全身に広がる場合もあります。シミやくすみと見分けがつきにくいこともあるため、「いつもと違う」と感じたら、早めに医療機関を受診しましょう。
黄疸の症状②尿や便の色が変わる
尿や便の色の変化も、黄疸に伴って現れる代表的なサインです。
- 尿の色がオレンジ色から茶褐色っぽくなる
- 便の色が白や黄色っぽくなる
尿の色が濃くなる理由は、血液中の直接ビリルビン(水に溶けやすいビリルビン)が増加し、腎臓から尿中へ排せつされるからです。 また便が白っぽい色になるのは、胆道(胆汁の通り道)が閉塞するなどの理由で、便の色素となるビリルビンが腸内に十分に排せつされなくなるからです。このように、排せつ物の色の変化は、黄疸の原因を推測する上でも重要な所見です。異常を感じたらすぐに医療機関を受診しましょう。
黄疸の症状③だるさ、食欲不振、かゆみ
黄疸が進行すると、見た目の変化だけでなく、体調にも影響が出てきます。特に「だるさ」「食欲不振」「かゆみ」は、よく見られる症状です。
黄疸の背景にある肝機能の低下により、休んでも強い倦怠感が取れなかったり、原因不明の食欲低下、体重の減少が起きたりすることがあります。
また、胆汁の流れが滞る「胆汁うっ滞」を伴う黄疸では、血中の胆汁酸などが皮膚を刺激することで、全身に強いかゆみが生じることもあります。
皮膚の黄色さは時に気づきにくく、だるさ、食欲不審、かゆみのみで医療機関を受診される方もいらっしゃいます。
これらの症状が見られた際は、早めに医療機関を受診しましょう。
黄疸の原因|病気と生活習慣の関係
黄疸は、原因によって大きく以下の4つのタイプに分類されます。
- 1. 肝臓の病気による黄疸
- 2. 胆道のつまりによる黄疸
- 3. 赤血球の溶血による黄疸
- 4. 新生児〜思春期の黄疸
それぞれのタイプについて代表的な疾患をあげつつ、解説していきます。
黄疸の原因①肝臓の病気による黄疸
肝疾患は黄疸の原因として最も一般的です。肝機能が低下するとビリルビンの処理が滞り、体内に溜まります。具体的には以下のような病気が関係しています。
| ウイルス性肝炎 | 特にB型、C型肝炎が多い |
|---|---|
| アルコール性肝障害 | 過剰な飲酒が原因 |
| 薬剤性肝障害 | 薬やサプリメントによる影響 |
| 自己免疫性肝疾患 | 自分の免疫が自分自身の肝臓や胆管を攻撃 |
| 肝硬変・肝がん | 上記の疾患が進行して起こる重篤な病気 |
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、異常を自覚しにくいのが特徴です。黄疸のように目に見える症状は数少ない外的サインなので、気になったらすぐに医療機関を受診しましょう。
肝臓の病気については、こちらの記事もご覧ください。

黄疸の原因②胆道のつまりによる黄疸(閉塞性黄疸)
胆汁の通り道である「胆道」が物理的に塞がれると、胆汁が流れなくなり、ビリルビンが体内に溜まって黄疸が起こります。このような状態を「閉塞性黄疸」と呼び、以下のような病気が原因となります。
| 総胆管結石 | 胆石が総胆管に詰まり、胆汁の流れを妨げる |
|---|---|
| 胆道がん | 胆嚢がん、胆管がん、十二指腸乳頭部がんなど |
| すい臓がん | 膵頭部にできた腫瘍が胆管を圧迫する |
| 良性胆管狭窄 | 慢性膵炎や手術後の癒着などが原因 |
中でも最も恐ろしいのがすい臓がんです。すい臓がんの初期は自覚症状がなく、黄疸が最初のサインになることもあります。しかし、症状が出たときにはすでに進行しているケースが多く、5年生存率*は全てのがんの中で最も低い12.1%とされています。
すい臓がんは早期発見が何よりも重要です。40代以降の方や家族歴がある方は、定期的なすい臓がん検査を受けることをおすすめします。すい臓がんの詳しい検査については以下をチェックしてください。
https://smartdock.jp/docks/cancer-pancreatic
*5年生存率:がんと診断された人が、5年後にどれだけ生存しているかを示す指標
黄疸の原因③赤血球の溶血による黄疸(溶血性黄疸)
赤血球が急激に壊れると、大量のビリルビンが発生し、肝臓で処理しきれず、体内に蓄積されるため、黄疸が引き起こされます。このような黄疸は「溶血性黄疸(肝前性黄疸)」と呼ばれ、主な原因には以下のような病気があります。
| 自己免疫性溶血性貧血(AIHA) | 免疫が誤って赤血球を攻撃する |
|---|---|
| 遺伝性溶血性貧血 | 赤血球の膜や酵素の異常(例:遺伝性球状赤血球症) |
| 発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH) | 夜間に赤血球が壊れやすくなる希少疾患 |
| 不適合輸血 | 血液型が合わない輸血により赤血球が破壊される |
これらの病気では、黄疸以外にも貧血や尿の色の変化が見られることがあります。

黄疸の原因④新生児期から思春期の黄疸
赤ちゃん、あるいは体質によっては思春期の子どもにも黄疸が見られることがあります。新生児に多いのは「生理的黄疸」で、多くは自然に治りますが、注意が必要なケースもあります。
生理的黄疸
新生児の肝機能が未熟なことや赤血球の寿命が短いことが原因で発生します。生後2〜3日で現れ、1〜2週間で自然におさまるもので、病的なものではありません。
母乳性黄疸
母乳に含まれる成分の影響で黄疸が長引くことがありますが、ほとんどは経過観察で問題ありません。
病的黄疸
生後間もなく強い黄疸が出る、急速に悪化する、長く続くといった場合は注意が必要です。先天性の重症の溶血、胆道閉塞、感染症などが背景にあることもあり、核黄疸を防ぐためにも早期の検査を推奨します。

また、思春期ごろに症状の出る、ジルベール症候群などの体質による黄疸では、通常は無症状ですが、ストレスや体調不良をきっかけに軽度の黄疸が出ることがあります。気になる場合は、早めに医師に相談しましょう。
黄疸に気づいたら病院へ行くべき?
黄疸に気づいた場合、原因を特定し、適切な対応をとるために、医療機関への受診が重要です。判断のポイントは以下の通りです。
-
新生児
生理的黄疸は通常生後1週間程度で軽快しますが、1週間以上経っても軽快せず、身体全体に黄色みが広がる、便が白っぽい、尿が濃い茶色である場合は、速やかに小児科を受診してください。 -
成人
黄疸は肝臓や胆道系の重篤な疾患のサインである可能性があるため、原則として早期の受診が必要です。特に、急に黄疸が出現した場合や、濃い色の尿、白い便、腹痛、発熱、倦怠感、食欲不振などの症状を伴う場合は、速やかに消化器内科を受診しましょう。
黄疸の検査
黄疸の原因を調べるには、以下の検査が行われます。
| 検査名 | 概要 |
|---|---|
|
血液検査 |
・ビリルビン値(総ビリルビン、直接ビリルビン、間接ビリルビン)を測定し、黄疸の種類を判別 ・AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの肝機能検査 ・CRP、白血球数で炎症の有無を確認 |
|
抗体検査 |
・自己免疫疾患など、免疫の異常がないかを判別 |
|
画像検査 |
・腹部超音波(エコー)検査により、肝臓や胆道の状態、胆石や腫瘍の有無を確認。初期検査として広く用いられる |
|
CT検査、MRI検査 |
・腫瘍の位置や胆道の閉塞、すい臓の異常などを精密に評価 |
|
MRCP検査 |
・MRIを用いて胆管やすい臓の周辺の病変を評価 |
|
その他の検査 |
・内視鏡検査(ERCP:内視鏡的逆行性胆管膵管造影など)や肝生検(肝臓の組織を採取して調べる検査)が必要になる場合もあります |
黄疸の治療方法
黄疸の治療は、原因となる病気によって異なりますが、主な治療法は以下の3つです。
| 光線療法 | 新生児黄疸で多く使われ、特殊な光でビリルビンを分解する |
|---|---|
| 薬物療法 | 肝臓や胆道の炎症、代謝異常などに対して薬を用いる |
| 内視鏡治療 | ステント挿入や胆石除去で胆汁の流れを回復する |
| 手術 | 胆石や腫瘍など、物理的な閉塞がある場合に行う |
早期検査によって原因を明らかにし、適切な治療を行うことで、重症化を防ぎ、症状の改善につながります。
黄疸の治療方法①光線療法
光線療法は新生児黄疸に広く用いられる治療法です。特殊な光を赤ちゃんの皮膚に当て、ビリルビンを水に溶けやすい形に変えて、尿や便として排出しやすくします。安全で効果的な方法ですが、治療中は目の保護や水分補給が必要で、通常は数日から1週間で改善が見られます。
黄疸の治療方法②薬物療法
薬物療法は、肝炎や胆道の炎症、ビリルビン代謝の異常などが原因の黄疸に対して行われます。炎症を抑える薬や胆汁の流れを助ける薬、代謝を促す薬などが用いられます。治療中は副作用や肝機能の変化に注意しながら、医師の指導のもとで慎重に治療が進められます。
黄疸の治療方法③内視鏡治療
胆道の閉塞が原因で黄疸が起きている場合、内視鏡的治療(ERCP)が行われることもあります。ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)は、口から内視鏡を挿入して胆管や膵管の状態を観察し、治療する方法です。狭くなった胆管にステント(チューブ)を挿入して胆汁の流れを回復させることや、胆石を取り除くことが可能です。開腹手術に比べて身体への負担が少ないですが、内視鏡治療は専門の技術と設備が必要であり、合併症のリスクについても医師とよく相談することが大切です。
黄疸の治療方法④外科手術
胆石や腫瘍などで胆道が塞がれている場合は、手術で胆汁の流れを回復させる必要があります。胆道の開通や病変の切除によって、体内にたまったビリルビンが排出されやすくなり、黄疸の改善が見込まれます。手術前後の検査や経過観察が重要なため、医師とよく相談しながら治療を進めていきます。

黄疸にならないようにするには?
黄疸は前述の通り、様々な原因により出現します。定期的に健康診断や人間ドックを受け、早期に黄疸となる原因疾患を見つけ出すことによって予防が可能と言えます。
まとめ|黄疸の症状に気づいたら早めの行動を
黄疸は、肌や白目の黄ばみ、尿や便の色の変化、全身のだるさやかゆみなど、さまざまな症状として現れます。新生児に多く見られるものから、肝臓や胆道の病気、赤血球の異常、遺伝的な体質まで、原因は多岐にわたります。黄疸のような目に見える症状は、身体からの重要なサインです。「様子を見よう」と先延ばしにせず、気づいたらすぐ医療機関を受診することが自分の健康を守るために重要です。 日ごろから定期的に健診や人間ドックなどを受診し、少しでも気になる症状があれば、早めに医療機関で検査を受けましょう。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
早期発見が難しいすい臓がんを
調べてみませんか?
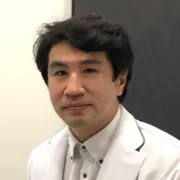
科目 内科・皮膚科・アレルギー科
2023年に千代田区神田で「スキマ時間に通える」をコンセプトとして忙しい方のために空いたスキマ時間、昼休みや仕事終わり、休みの日にも通える内科・皮膚科・アレルギー科のクリニック「クリニックファーストエイド」を開設。





