糖尿病でも食べていいお菓子ってあるの? 間食の仕方や注意点をご紹介
糖尿病の患者が食べでもいいお菓子と食べてはいけないお菓子について具体的に紹介しています。またお菓子以外に間食としておすすめなものや、間食をする際のポイントなどについてもわかりやすく解説しています。糖尿病の方でも一緒に間食を楽しめるように、どんなものを食べてもよく、何がNGなのかみてみましょう。糖尿病とは? 1型と2型の違いや、症状、合併症などについて解説します!
 163
163
糖尿病とは?

糖尿病とは慢性的に高血糖の状態になる病気です。
血液中の糖が増えすぎると、血液の流れを妨げるだけでなく、「活性酸素」の発生を促し、血管を傷つけ、動脈硬化等様々な病気を引き起こします。
糖尿病の合併症として網膜症、腎症、神経障害が有名で、各器官を障害し、生活への影響または生命にも危険を及ぼす可能性があります。
糖尿病の原因
高血糖になる原因はインスリンの分泌量の低下、またはインスリン抵抗性が高くなることです。インスリンは血管内にある糖を肝臓や筋、脂肪組織に取り込むとともに、糖を作り出すことを抑制する働きを持っています。
インスリンは、血糖を下げる働きをもつ唯一のホルモンです。これらの機能がもし十分に発揮されなければ、糖は血管内にあふれることになり、さまざまな障害を引き起こします。
インスリン分泌量低下
インスリンはすい臓で作られています。
すい臓の機能が低下したり、インスリンを作る細胞自体が破壊されてしまうと、インスリンを作り出すことができないため分泌量が減ります。
そもそものインスリン量が減ってしまうと、それだけ糖の取り込みも減るため高血糖につながってしまいます。
インスリン抵抗性
「インスリン抵抗性が高い」とは、インスリンが各細胞に働きかけた際に、細胞が糖を取り込みにくい状態のことです。
つまり「インスリン抵抗性が高い」=「インスリンが効きにくい状態」です。
インスリン抵抗性を引き起こす主たる原因は、肥満です。
糖尿病の種類
糖尿病はおもに「1型糖尿病」と「2型糖尿病」にわけられます。
これらは原因が異なるため、治療法にも違いがあります。
発症の割合としては2型糖尿病がほとんどで、生活習慣の改善で予防することができます。
1型糖尿病
1型糖尿病は、主に自己免疫学的機序により、すい臓にあるインスリンを分泌するβ(ベータ)細胞が破壊され、インスリンが出なくなるために高血糖状態となり、糖尿病となります。
本来外敵から体を守るために働くはずの免疫が、間違ってβ細胞を標的にしてしまい、破壊してしまいます。自己免疫が働いてしまう詳しい原因はまだわかっていません。
2型糖尿病と違い、生活習慣は糖尿病の発症に無関係です。
1型糖尿病の方は自身でインスリンを作り出すことができないため、治療としてインスリン注射が必要になってきます。
2型糖尿病
生活習慣や遺伝要素により、インスリンの分泌量の低下や、インスリン抵抗性の向上が起きたものを「2型糖尿病」と呼びます。
肥満の方に発症しやすいですが、遺伝的な要因もあるため限定はされません。
| 1型糖尿病 | 2型糖尿病 | |
|---|---|---|
| 原因 | 自己免疫性 | 生活習慣、遺伝要因 |
| 患者の特徴 | 小児~思春期の子供、やせた人 | 中高年(40歳をすぎた方がほとんど)、肥満に多い |
| インスリン抵抗性 | 低い | 高い(程度はそれぞれ異なる) |
| 症状の進行 | 症状が突然出現 | ゆっくり進行していく |
糖尿病の症状

糖尿病は初期段階では自覚症状が全くない事が多く、症状があらわれるとしても、非常にゆっくりです。
【糖尿病の症状】
・のどがよく渇く
・尿の回数が増える
・疲れやすくなる など
糖尿病自体の症状は上記で挙げたものが中心になりますが、糖尿病は合併症による障害が起きやすいです。そこで糖尿病の合併症について詳しく解説していきます。
糖尿病の合併症
体には細い血管と太い血管がありますが、糖尿病の合併症ではそれぞれどちらの血管が傷ついたかで体に起きる影響が異なります。
【細い血管が傷ついた場合】
- 糖尿病性神経障害
- 糖尿病性腎症
- 糖尿病性網膜症
これらは糖尿病の三大合併症とも呼ばれています。
糖尿病性神経障害
糖尿病性神経障害は、過剰な糖により神経に栄養を送る血管に障害が起こることなどで発症します。
三大合併症の中では、最も症状が現れる頻度が高いとされています。
症状は手足のしびれ、感覚のにぶさ、排尿障害などがあります。
治療方法は血糖のコントロールを大前提にして、現れた症状に合わせて薬物療法などを行います。
糖尿病性腎症
糖尿病性腎症は、糖尿病に罹患して10~15年以上経過してから発症することが多いです。
腎臓の機能が落ちていくと、早期は無症状ですが、進行すると体の余分な水分や老廃物を体外に出す機能が弱まるため、むくんだり、気分が悪くなったりします。
放置しておくと人工透析が必要になることもあります。
しかし早い段階で治療を行うことで改善も可能ですので、何らかの異常が見られた際は早急に医師に相談する必要があります。
糖尿病性網膜症
糖尿病性網膜症は段階的に進行していく網膜の病気です。
初期の段階では症状に気づきにくく、進行すると最悪の場合には、眼底出血や網膜剥離で失明する可能性もあります。
網膜症を悪くしないためには、血糖のコントロールが必要です。早い段階で網膜症を見つけておけば(例えば糖尿病と診断されたすぐ後など)レーザー治療で出血を予防できる場合もあります。
糖尿病の検査・診断方法
① 空腹時血糖値が126mg/dl以上
② 随時血糖値(時間関係なく測定した血糖値)が200mg/dl以上
③ 75g経口ブドウ糖負荷試験2時間値(糖を摂取してから2時間後の血糖値のこと)が200mg/dL以上
④ HbA1c(1~2か月間の血糖値の平均が反映されるもの)が6.5%以上
①-③のいずれかと④が確認された場合、糖尿病と診断されます。
糖尿病の治療方法
糖尿病になれば、かならず合併症を併発するわけではありません。
合併症を発症しないためには、早めの治療が必要です。
1型糖尿病では、基本的にインスリン注射になります。
◇補足◇
現在は経口でのインスリン投与ができるように研究がすすめられています。
詳しく知りたい方はこちらの記事(『「経口インスリン」を開発 インスリンを錠剤にして糖尿病の人の負担を軽減』)を読んでみてはいかがでしょうか。
ここからは、2型糖尿病の治療方法を中心に解説していきます。
食事療法
1日3食、栄養バランスの良い食事を心がけます。
間食は基本的には控えた方が良いです。
しかし、今まで習慣的に間食をとっていた方は、突然やめることは大変だと思います。糖尿病に影響しにくいお菓子もあるため、どうしても間食をしたいときには影響の少ないお菓子を選ぶ必要があります。

運動療法
運動をすることで、インスリン抵抗性を改善し糖の取り込みを促進する効果があるとされています。
また他にも運動をすることで、肥満の解消や心肺機能向上、動脈硬化の予防なども期待されます。
肥満の解消自体、インスリン抵抗性の改善につながるため、効果的です。
自身に適した運動量を医師と相談して決めましょう。
世界一座りすぎの日本人! 長時間の座りっぱなしは肥満のリスクが上昇?!
1日を振り返ってみると、座りすぎている気がするという方は多いかと思います。座りすぎは血中の脂質量の上昇などにつながり、肥満や心疾患、糖尿病のリスクも高まるといわれています。今回の記事では座りすぎが体に与える悪影響などについて解説したします。
薬物療法
食事療法や運動療法での改善が期待できない場合は、薬物療法を行います。
薬物療法でも効果が得られない場合は、インスリン注射を行います。
糖尿病の予防方法

2型糖尿病は生活習慣の乱れが原因の場合が多いです。
日頃の意識で、糖尿病の予防や悪化を防ぐことができるので、この機会に生活習慣を見直すことをおすすめいたします。
ここでは食習慣と運動に焦点を当てて、ご紹介していきます。
食習慣の見直し
インスリン分泌機能を向上したり抵抗性を改善する食材や、糖の少ない食材の摂取が、糖尿病の方では好ましいです。
【糖尿病の予防におすすめの食材】
・野菜
・海藻類
・キノコ類
・豚肉
・青魚 など
【避けた方が良い食材】
・白米(玄米や胚芽米はインスリン分泌を促進するとされている)やパン類
・果物
・いもなどの甘い野菜
・お菓子 など
運動習慣の見直し
上記でも解説したように、運動をすることで肥満の解消などにより、インスリン抵抗性の改善を図ることができます。
【糖尿病の予防に効果的な運動】
・自身の体型や身体機能に合わせた適切な強度の運動
・買い物などでエスカレーターやエレベーターではなく階段を使用
・ウォーキングやランニングなどの有酸素運動 など
普段、運動習慣がない方は、生活の中に少しだけ意識して運動を取り入れることから始めてみましょう。
糖尿病は早期発見・早期治療開始が重要!
生活習慣の乱れが糖尿病の原因のひとつであるため、日常の食習慣や運動習慣を見直して、健康的な生活を送ることが糖尿病予防には大切です。
糖尿病は自覚症状が出にくいうえ、さまざまな重篤な合併症を引き起こす可能性もあります。
糖尿病の予備軍段階で早期発見できるよう、年1回の健康診断や人間ドックの受診をおすすめいたします。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
脳の健康状態を調べてみませんか?
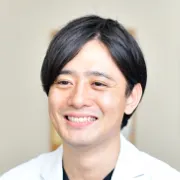
京都府立医科大学卒業後、虎の門病院入職。内科全般を学び、その後がんや慢性疾患を多く扱う消化器内科医に。『健康防衛・健康増進』の重要性を痛感。『患者様の健康増進のために本気で取り組みたい』という強い想いで、愛和クリニック開業。


