この肺炎の症状に注意! 特に肺炎に気をつけるべきなのはどんな人?!
 1102
1102
肺炎とは?

鼻や口から吸い込まれた空気は、喉から空気の道(気管)を通って肺へと到達します。
肺の奥には肺胞と呼ばれる部分があり、肺胞やその周辺組織に炎症が起こった状態を「肺炎」と言います。
肺炎は決して軽い病気ではありません。
風邪をこじらせて肺炎になったと聞くと、大したことがないという印象を受けてしまう方も多いと思います。
しかし、風邪よりも長い治療期間が必要で、重症化すれば命に関わります。
肺炎の疑いがある際には絶対に放置をせずに、速やかに医師の診断を受けましょう。
肺炎の種類と原因
肺炎の原因の多くには病原菌(細菌、真菌、寄生虫など)が関係しています。
吸い込んだ空気には無数の目に見えない微生物がいて、その微生物の一部が悪さをしてしまうことがあります。
病原菌を吸い込んだからといって必ず肺炎になるわけではありませんが、体調や環境を含めて様々な原因が重なり合って肺炎を起こします。
感染性肺炎
肺炎を起こす病原菌や病原体は大きく4つに分けられます。
これらの微生物などが肺に入った後、人体の免疫によって排除されなかった場合に肺炎を起こす可能性があります。
細菌(バクテリア)
ブドウ球菌、肺炎球菌、抗酸菌、インフルエンザ菌などが含まれます。
抗生物質で対処できる細菌もいます。
ウイルス
細菌よりもさらに小さい分子で、インフルエンザウイルス、アデノウイルス、新型コロナウイルスなどが含まれます。
抗生物質は効きません。
ウイルスによる肺炎を起こした後に、さらに他の細菌などが肺炎を起こすこともあります。
マイコプラズマ
細胞壁を失った細菌のため、細胞壁の合成を阻害する抗生物質が効きません。
真菌(カビ)
「肺真菌症(はいしんきんしょう)」とも呼びます。
カンジダやアスペルギルス、クリプトコッカスなどのカビによって起こった肺炎の状態です。
非感染性肺炎
肺炎は感染が原因で起こりますが、感染とは無関係に「肺炎」と名前がついている病気もあります。
感染とは別の原因で肺に炎症などが起こり、機能が損なわれた状態で、「肺疾患」と考えるほうがわかりやすいでしょう。
間質性肺炎
肺が何かしらの原因から線維化してしまう病気で、進行した場合には「肺線維症」とも呼ばれます。
自己免疫性疾患や薬剤が原因で起こることもあります。
またウイルス感染の中には、間質性肺炎の形で炎症を起こすものが含まれます。
肺水腫など
重度の肺炎や心臓病などが原因で、肺胞に水が溜まってしまうことがあります。
肺炎の症状
肺炎は肺に障害が起こった状態で、一般的には風邪の症状や、風邪がさらに重くなった症状が多く見られます。
しかし肺炎が起こってしまうと、長期間の療養を必要とすることや、場合によっては重症化をして命に関わることもあります。
風邪のような症状は必ず現れるとはいえません。
特に乳幼児や高齢者では、目立った症状がなくても肺炎が起こっているケースや、突然の重症化により発見されるケースもあります。
肺に炎症が起こった時に現れやすい症状としては、以下のものが挙げられます。
咳

空気を吸い込む時に細菌や真菌も一緒に吸い込まれますが、粘液(痰)として排出されます。
異物を排除しようとする「咳」も、肺炎が起こっている時にはさらに重くなります。
肺炎では痰に特徴的な色(黄色や緑色など)がついたり、血が混じったりすることもあります。
また痰を伴わない咳(空咳)が特徴的な肺炎もあるので、注意しましょう。
発熱

体温を上げて身体を守ろうとする場合があり、39.0度以上の高い体温となることもあります。
高熱が長時間続くと身体が耐えきれず、いろいろな症状が出てきます。
発汗などによる脱水症状を防ぐためにも、水分補給は忘れずにしましょう。
意識が混濁するなどの症状がある場合には、特に注意が必要です。
呼吸困難

気管や肺が炎症によって狭くなったり、肺胞に水が溜まったりした状態では呼吸をすることが難しくなります。
息をするたびに「ビュービュー」「ピーピー」「ゼーゼー」などの音(喘鳴)が出ることも多くあります。
呼吸が難しくなると、顔や唇などの血の気が失せて紫色に変色(チアノーゼ)することもありますので注意しましょう。
胸の痛み

肺の炎症が広がって肺を覆う部分にまで広がってしまうと、強い胸の痛みを感じることがあります。
また重い咳や長く続く咳によっても、筋肉痛によって胸の痛さが出てきます。
咳では喉や胸など広範囲に痛みを感じることがありますので、強い痛みがある時には医師に相談をしましょう。
横になると咳が出るのはなぜ? 肺炎のサインと対処法
「横になると咳が出る」「寝る時に咳が出る」といった症状には、いくつかの原因が考えられます。例えば「喉や気道に分泌物が溜まっている」「心臓の働きが悪くなっている」「胃酸が逆流している」などです。
また、仰向けの姿勢では気道が圧迫されやすく、咳反射が起こりやすくなります。これらは、風邪や喘息などでも見られる症状ですが、咳が止まらず息苦しさを伴う場合は、肺炎の可能性もあります。「熱がある」「咳が激しい」「呼吸が浅くゼーゼーする」「胸が痛む」といった症状が同時に現れる時には注意が必要です。
就寝時は枕を高くして上半身をやや起こした姿勢を保つことで、咳が落ち着くことがあります。その際は、顎を引きすぎて気道を塞がないように気をつけましょう。乾燥を防ぐために、加湿器やマスクを使用するのも効果的です。
肺炎の診断方法
肺炎が疑われる時には、医師が症状などを確認した上で処置を進めていきます。
一般的には、肺炎の初期に見られる咳や熱などの症状がある時には、X線検査や胸部CT検査といった画像診断により肺炎像の有無や、肺炎の原因を調べます。
また、並行して血液検査で炎症のマーカーなどを用いて肺炎の診断を行います。
肺炎をセルフチェックできる? 「息を止める検査」の真実
インターネット上では「息を止める検査」による肺炎のセルフチェックが広まっていますが、科学的な根拠がありません。この方法で肺炎が診断できるというのは誤りのため注意しましょう。
肺炎の診断は医師により行われます。例えば、診察による呼吸状態のチェック、胸部X線検査、血液検査などにより医師が総合的に肺炎の有無を判断するのです。
肺炎が疑われる場合には、まずは以下のような症状の有無を確認してみましょう。
- 胸の痛みがある
- 高熱や寒気がある
- 咳が出続ける
- 痰が増加している
- 急に息苦しくなった
- 唇が紫色になっている
- 横になれない、座らないと息ができない
これらの症状がある場合は、自己判断せず、すぐに医療機関を受診しましょう。
肺炎は放置すると重篤化する恐れがあります。そのため、医療機関により専門的な診断や治療を受けることが重要です。
なお、「症状はないけど、検査はしてみたい」「予防的に健康管理はしておきたい」といった方は人間ドックの利用を検討するのも良いでしょう。スマートドックでは気になる部位をピンポイントで調べられます。気になる方は以下から詳細を確認してみましょう。
肺炎になったらどうする? 肺炎の時の過ごし方
肺炎と診断された方が自宅で療養する場合、安静と休養がとても大切です。肺炎は体力を大きく消耗する病気で、無理をすると症状が悪化する恐れがあります。
自宅療養のポイントは以下の通りです。
- 十分な休養を取る
- 水分補給と栄養補給を心がける
- 薬は医師の指示通りに内服する
- 感染拡大の防止を徹底する
体力の回復には、十分な休養や睡眠が重要です。特に、適切な睡眠は身体の免疫力を高めると言われています。体力を消耗しないよう、無理に身体を動かさずできるだけ横になって過ごしましょう。

水分補給、栄養補給も重要です。肺炎になると、発熱や咳などにより体内の水分が失われやすくなります。過度の体力低下や脱水症を起こさないために、こまめに水分を補給しましょう。また、ビタミンやタンパク質は、体力や免疫力の維持につながります。これらを意識しながら、栄養バランスの取れた食事を摂りましょう。
処方された薬、特に抗生物質は、自己判断で中止せず医師の指示通りに服用しましょう。指示通りに服用することで、治療効果が最大限に発揮されます。一方で「もう良くなったかも」と、途中で服用をやめてしまうと、治りきらず再発したり、かえって悪化したりする可能性があるため注意しましょう。
周囲への感染拡大を防ぐため、自分と周囲の人のマスクの着用や手洗い、うがいを徹底するのも重要です。家族や同居者がいる場合、共用スペースの消毒も行いましょう。
肺炎の治療方法
肺炎の原因によって治療方法が異なってきます。
細菌や真菌など抗生物質が効く原因に対しては、抗生物質による原因の除去を進めます。
ウイルスに対しては抗生物質が効かないため、細菌などの重複した感染を防ぐ目的で抗生物質を使用することがあります。
軽度の肺炎の場合、解熱鎮痛剤や咳止めなどの対症療法を行うことがあります。
しかし重度の肺炎で呼吸機能に問題がある場合には、ICU(集中治療室)で挿管の処置が必要となる場合があります。
こんな人は肺炎にかかりやすいので注意!
肺炎は肺に病原菌や病原体が侵入することで起こりますが、健康な方であれば、通常は身体の免疫機能によって肺炎を起こさずに済みます。
しかし肺炎になるリスクが高い方もいます。特に免疫が弱い状態では、健康な方ではあまり肺炎を起こさない原因菌で肺炎を起こしてしまうこともあります。
以下の項目に該当する方は、肺炎に対しての予防や警戒が特に必要といえるでしょう。
- AIDSなどの免疫不全の方
- 高齢で免疫機能が低下している方
- 免疫抑制の薬などを使用している方
- 脳血管障害(脳梗塞、脳内出血など)に罹患している方
- 呼吸器疾患(肺気腫、肺結核後遺症、間質性肺炎など)に罹患している方
- 心疾患に罹患している方
- 腎臓病に罹患している方
- 糖尿病に罹患している方
- がんに罹患している方
肺炎の予防方法

肺炎を予防するには、基本的には風邪の対策と同じく手洗いやうがい、マスクなどを心がけることが大切です。
他には誤嚥性肺炎を防ぐための「嚥下トレーニング」、喫煙する方は禁煙も意識しましょう。
肺炎を起こす原因は多数ありますが、肺炎球菌やインフルエンザなどが原因となることもあります。
そうした病原菌や病原体に対しては、「ワクチン」を接種して予防することも効果的です。
何よりも風邪の症状が長引いたり、重い咳が出たりする場合には自己判断をせず、早い段階で医師の診断を受けましょう。
まとめ
肺炎は重症化すると命に関わる可能性がある病気です。初期症状が風邪と似ているため見逃されがちですが、「咳が長引く」「発熱が続く」「息苦しい」などの症状があれば早めに受診することが大切です。特に発熱、夜間や横になった時の咳、強い倦怠感などは見過ごさないようにしましょう。
また、誤ったセルフチェックに頼らず、医師の診断を受けて適切に治療することも重要です。正しい知識を持ち、無理をせず安静に過ごすことが回復への近道になるでしょう。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
気になる方は、即日予約・受診可能です。
所要時間10分、検査は3分の
「胸部CT肺ドック」
 まずは空き枠を確認してみる
まずは空き枠を確認してみる
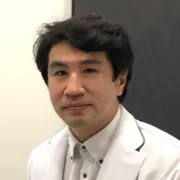
科目 内科・皮膚科・アレルギー科
2023年に千代田区神田で「スキマ時間に通える」をコンセプトとして忙しい方のために空いたスキマ時間、昼休みや仕事終わり、休みの日にも通える内科・皮膚科・アレルギー科のクリニック「クリニックファーストエイド」を開設。




