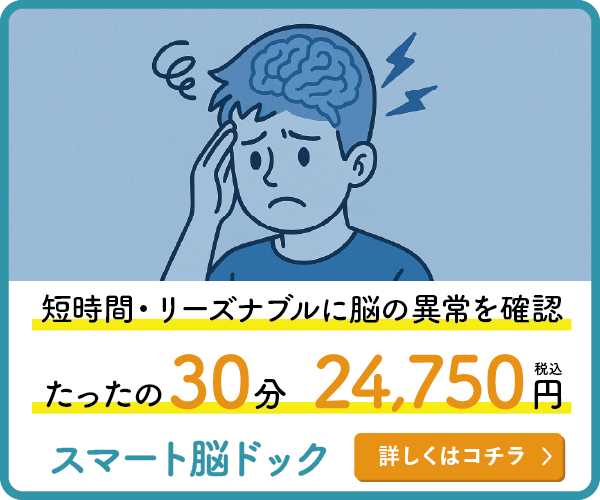血圧管理には減塩が効果的! 1日の目標とすべき塩分「6g」ってどの程度?
高血圧には減塩が効果的であると言われています。この記事の中では、血圧上昇による腎臓や心臓への負担についてご紹介します。また1日で目標とすべき塩分の摂取量は6g程度ですが、6gとは実際にはどのくらいなのでしょう? 身近な食品や調味料に含まれる塩分量について知り、食生活を見直すきっかけにしてみてください。脳出血とはなにか? 出血しやすい部位や体に起こる症状について解説
 319
319
脳出血(脳内出血)ってどんな病気?

脳出血とは、脳の動脈が破れることで、脳の中に出血した状態のことです。
脳の血管から流れ出た血液が脳の神経細胞を圧迫することで障害が起き、頭痛、手足のまひ、吐き気などの症状を起こします。
症状は脳内のどこで血管が破れたか、また流れ出た血液の量によっても異なります。
脳出血のおもな原因
脳出血のおもな原因としては、高血圧があげられます。
高血圧は動脈に負担をかけるため、長い間高血圧がつづくと血管が次第に脆くなってしまい、ついには破れてしまうのです。

また高齢者の場合には、脳血管に異常なタンパク質が沈着する病気である脳アミロイド血管症により、血管が脆くなって破れてしまうことがあります。
その他にも、脳動静脈奇形やもやもや病などでも脳出血が生じることがあります。
脳出血の種類
脳出血は脳の部位によって特徴的な症状や原因があり、だいたい5種類に分けることができます。
| 出血する部位 | 起こる症状や特徴 |
|---|---|
| 被殻(ひかく) | 高血圧性の脳出血の中ではもっとも頻度が多い。 頭痛や嘔吐が先行して起こり、手足が動かなくなる方が多い。 死亡率はそれほど高くないが、意識状態や出血量によって手術を検討する必要がある。 |
| 視床(ししょう) | 脳出血の約3割程度にみられる。症状はしびれ、まひ、感覚障害など。 後遺症が残ってしまうケースが多く、合併症として「急性水頭症」が起こることがある。 |
| 小脳 | 頭痛、嘔吐、めまいが起こる。 出血が始まった当初は意識障害はない場合でも、徐々に意識障害が起こることがある。 血腫の大きさによって手術を検討する必要がある。 |
| 橋(脳幹) | 脳出血の約1割程度にみられる。 意識障害、呼吸障害、両手足のまひ、眼球運動障害などがみられることが多い。 発作から数分で昏睡状態になり、数時間で死亡するケースもある。 |
| 皮質下 | 脳葉出血ともいわれ、前頭葉や頭頂葉など大脳の表面に近い場所で起こる出血。 症状としてはけいれんや、軽めの意識障害などがみられる。 他の部位からの脳出血よりも比較的症状が軽い場合が多く、予後が良好なことが多いとされる。 |
脳出血の初期症状

脳出血の初期症状は、出血を起こした場所や出血量でかなり違いがみられますが、多くみられるのは以下の症状。
- 片側の手足のまひ、しびれ、しゃべりにくさ、歩きにくさ(運動の症状)
- 頭痛、めまい、吐き気、嘔吐(感覚の症状)
脳出血の診断方法
CT検査によって確定診断が可能。同時に出血した部位や出血量を調べることもできます。
さらに出血の原因を調べるために、追加でMRI検査や造影剤を用いたCT検査を行うこともあります。
また場合によっては、カテーテルを用いた「血管造影検査」が行われることもあります。
脳出血と似た症状(頭痛、めまいなど)があるけれど別の疾患が疑われる場合には、他の検査を行うケースもあります。
脳出血の治療方法
脳出血の原因は高血圧によるものが多いため、血圧を下げる薬が投与されます。
また、出血を止めるための薬や、脳が出血塊によって圧迫されるために起こる浮腫(むくみ)を取るための薬なども投与されます。
出血量が多い場合は命に関わることもあるため、頭の骨を外して血の塊を取り除く手術が行われることもあります。
また、急性水頭症が生じた場合には、髄液を体外に排出させる処置(脳室ドレナージ術)を行うこともあります。
ただし出血した場所や出血の状態によっては手術ができないこともありますので、医師とよく相談することが重要です。
脳出血の予防方法
脳出血のリスク低減には、おもな原因のひとつである高血圧を予防するために、生活習慣を少しでも健康にすることが大切です。
生活習慣の改善
高血圧をはじめとする生活習慣病は脳卒中のリスク要因となります。
血圧がすでに高い方は食事の塩分量や、脂質の取りすぎ、飲酒量にも注意することが必要です。
また食事と合わせて、日々の運動習慣によって体重コントロールをすることも大切です。
肥満は高血圧のみならず、糖尿病や脂質異常症などの危険性も上がります。
規則正しい生活と運動による健康の維持が重要です。
また、喫煙は血管を収縮させてしまうため、脳卒中の大きなリスクとして知られています。
▽以下の記事もぜひ読んでみてはいかがでしょう。

内臓脂肪を落とすにはどうする? 超悪玉コレステロールが動脈硬化を起こす仕組みも解説
内臓脂肪が体に溜まっていると動脈硬化につながる要因になりやすく、最悪の場合には大きな脳疾患を引き起こすことも。「自分は太っていないから大丈夫」そんな風に思っている方の中にも、じつは内臓脂肪が多い方がいます。内臓脂肪がどんな風に人体に悪影響を与えるか知ることで、脳疾患リスクについて学びましょう!
定期的に脳ドックを受ける

脳の健康診断である脳ドックを受診することで、脳卒中のリスクがあるかどうかを確認することができます。
ご自身の脳の状態を理解して少しずつ生活習慣を変えていくことが、さまざまな脳疾患を発症させないためには重要です。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
脳の健康状態を調べてみませんか?

28年間の脳神経外科の手術と救急の経験から、再生しない脳という臓器の特性、知らないうちに進行し突然発症して障害を残す脳卒中疾患の特性に対しては「発症させない」ことが最も有効な対策だと考えています。 なるべく多くの方が健康なうちに脳ドックを受診し、問題解決できる環境を提供してゆきたいと思います。