日中の眠気がつらい! 自分では気づかない睡眠中のいびきが原因かも? 睡眠時無呼吸症候群について解説!
「いびきがうるさい」「呼吸が止まってた」などと、誰かから指摘されたことはありますか? いびきをかいている方の中には、睡眠中に無呼吸状態に陥っている方が多くおられます。これは睡眠時無呼吸症候群(SAS)と呼ばれ、体に蓄積的なダメージを与えるものです。この記事の中では、慢性的ないびきが持つ危険性について、詳しくご説明いたします。どこからが肥満? 治療が必要になってしまう状態とは? 治療法についても解説!
 29
29
肥満は病気のもと
ヒトは加齢とともに筋肉量や骨量が減少して、体を支える力が弱まっていきます。
肥満とは脂肪が体に多く溜まった状態ですが、ただでさえ筋肉量や骨量が減っているところで体重増が起きると、骨や関節に対しても大きな負担がかかります。
また、肥満は糖尿病や高血圧などの生活習慣病を発症するリスクも高めます。
そのほかにも睡眠時無呼吸症候群、脂肪肝、痛風、全身のがんの発症とも肥満は密接に関係しています。

脂肪肝はどうやって治せばいいの? 血液検査だと発見できない場合もあるってほんと!?
アルコールによる肝機能障害はよく知られていますが、お酒をあまり飲んでいない方でも、脂肪肝になる方が増えています。脂肪肝は自覚症状がほぼないため、健康診断で指摘されても気にしないことが多いです。しかし脂肪肝は放置しておくと脂肪肝炎になってしまい、その後は肝硬変や肝がんになってしまう方もいます。
肥満の原因
肥満の原因としては以下のものが挙げられます。
・1日の摂取エネルギーが消費エネルギーより多い
・間食や過度な飲酒
・食事リズムが不規則
・運動不足
・過度な糖分摂取 など
現代ではコンビニエンスストアなどでいつでも食べ物を気楽に購入することができます。
飲料もスポーツドリンク、炭酸飲料、加糖コーヒーなど、砂糖が入った飲み物を頻繁に摂取することで、摂取カロリーは1日で消費できない量になってしまいがちです。
肥満の判断基準
肥満の度合いを判定するには、BMI(Body Mass Index)が用いられます。
BMIは体重(kg)÷ {身長(m)の2乗}で求めることができますが、男女とも標準とされるBMIは22.0です。
この数値は肥満と特に関連性が深いといわれている糖尿病、高血圧、脂質異常症にもっともなりにくい数値であるとされています。
◇日本国内のBMI指標による分類
25以上:肥満場合が多い体型
18.5~24.9:標準体型
18.5未満:痩せ体型
内臓脂肪と皮下脂肪の違い
脂肪はつく場所によって、おもに「内臓脂肪」と「皮下脂肪」にわけられます。

内臓脂肪は男性につきやすく、皮下脂肪は女性につきやすいです。
皮下脂肪よりも内臓脂肪が体につく方が、生活習慣病のリスクを高めることが知られています。
内臓脂肪
内臓脂肪は文字通り、内臓のまわりにつく脂肪のことで、皮下脂肪と比べて蓄積されやすいことで知られています。
蓄積されると血液中の悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪が増え、動脈硬化のきっかけをつくることになります。
また糖尿病、脂質異常症、高血圧などにつながる可能性もあります。
しかし、内臓脂肪は蓄積されやすいぶん、食事制限や運動量を増やすことで比較的簡単に減らすことが可能です。
皮下脂肪
皮下脂肪は皮下につきやすい脂肪です。
内臓脂肪にくらべると蓄積しにくいですが、消費もしにくい脂肪です。
皮下脂肪は内臓脂肪とくらべると、生活習慣病につながりにくい脂肪として知られています。
しかし、体には脂肪による重さが負荷となって膝を痛めてしまう原因となり、結果として活動量が減ることもあります。
高齢者の場合には特に注意が必要といえるでしょう。
| 蓄積しやすさ | 燃焼しやすさ | 生活習慣病リスク | |
|---|---|---|---|
| 内臓脂肪 | 〇 | 〇 | 高い |
| 皮下脂肪 | △ | △ | 低い |
治療が必要な肥満とは?
治療が必要な肥満として、肥満症と高度肥満症があります。
日本肥満学会による「肥満症診療ガイドライン2016」では、以下のフローチャートで分類します。
肥満症診断のフローチャート

*常に念頭に置いて診療する
** 肥満症の診断基準に必須な健康障害
耐糖能障害(2型糖尿病・耐糖能異常など)
脂質異常症
高血圧
高尿酸血症・痛風
冠動脈疾患:心筋梗塞・狭心症
脳梗塞:脳血栓症・一過性脳虚血発作(TIA)
非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)
月経異常・不妊
閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)・肥満低換気症候群
運動器疾患:変形性関節症(膝・股関節)・変形性脊椎症、手指の変形性関節症
肥満関連腎臓病
*** 肥満、高度肥満でも減量指導は必要
肥満症・高度肥満症の治療方法
肥満症、高度肥満症は、医師の指導のもとで治療が行われます。
治療の目標は肥満にともなう健康障害の解消、あるいは軽減や予防です。
肥満症の場合には現体重の3%以上、高度肥満症の場合は現体重の5%〜10%の減量を目指して、体重とともにウエストを計測しつつ、食事療法、運動療法、行動療法を組み合わせて目標達成を目指します。
食事療法
肥満症に対する食事療法の基本は、摂取エネルギーの制限です。
1日あたりの摂取エネルギー量は「25kcal×標準体重/日」が目安で、3〜6ヶ月で3%以上の体重減少を目指します。
BMI35以上の高度肥満症では、より厳格な食事療法が行われます。
◇具体的な改善案は?
バランスのいい食事を取りながら、糖の過剰な摂取と中性脂肪を増やす原因になるといわれている「飽和脂肪酸」の摂取をできるだけ控えることをおすすめします。
食事は3食をしっかり食べて、間食や夜食は控えましょう。
またアルコールに関しては、適度な量を心がけるようにしてください。
仕事の付き合いなどでお酒を飲む際は、食べものにも注意が必要です。 揚げ物を控えて、脂肪分の少ない食材を選びましょう。
ご自宅で飲む際にも、スナック菓子などをつまみにしないようにして、脂肪分の摂取量を減らして摂取エネルギーを減らしましょう。
運動療法
運動療法は減量、肥満予防に有用です。
運動療法プログラムの原則は、以下の表のようになります。
運動療法のプログラムの原則
| 頻度 | ・ほぼ毎日(週5日以上)実施する ・運動の急性効果を期待しなくてもいい場合、運動量が十分であれば週5日未満でまとめて運動してもいい |
|---|---|
| 強度 | ・安全性のため、当初は低〜中強度の運動から開始する ・運動に慣れてきたら強度を上げることも考慮する |
| 時間 | ・1日合計30〜60分、週150~300分実施する ・1回10分未満の中強度以上の運動を積み重ねてもいい |
| 種類 | ・有酸素運動を主体とし、レジスタンス運動、ストレッチング、種々のコンディショニングエクササイズを併用する。本人が楽しめて習慣化できる種目を見つけるよう促す ・日常の生活活動も増加させる ・座位時間を減少させる |
| その他 | ・個人への減量支援では、心肺運動負荷試験(CPX)による最大酸素摂取量、無酸素性作業閾値の測定は必須ではない |
◇具体的な改善案は?
運動はウォーキングやランニングなどの有酸素運動が効果的です。
中強度の長め(30分程度)の運動を行うことで、脂肪が燃焼されやすくなります。
日頃から運動不足の方は、エスカレーターやエレベーターではなく階段を使ったり、車を使うのではなく歩いたりと、少しだけでも運動する意識をするだけでもいいです。
自分のペースで継続することを目標にしましょう。
肥満は心筋梗塞や脳梗塞のリスクが上昇
心臓や脳の血管が詰まり、動脈硬化を起こし、血流が悪くなり組織が壊死してしまうことが心筋梗塞や脳梗塞です。
内臓脂肪型肥満が動脈硬化を発症させる理由として、脂肪細胞から分泌されるアディポサイトカインがあります。 糖尿病や動脈硬化を防ぐとされているアディポサイトカインが分泌されていていますが、内臓脂肪が蓄積するとその分泌が低下して、動脈硬化の原因となります。
心筋梗塞や脳梗塞の要因として、内臓脂肪が蓄積すると脂肪細胞から血栓ができやすくなるPAI-1という物質が多く分泌されるため血管がつまりやすくなります。
また、脳梗塞は範囲が大きいと、さまざまな身体上の障害につながる可能性もあります。
脳梗塞の種類は大きく3種類! 症状ごとに知っておくべき特徴とは?
脳梗塞は脳内の動脈が狭くなったり、血栓で閉塞してしまったりすることで発症します。脳梗塞の範囲が大きいと、さまざまな身体上の障害につながる可能性も。では、記事の中で詳しくみていきましょう。
生活習慣の見直しをしましょう

BMIが25を超えると生活習慣病のリスクが高まります。
特に内臓脂肪型肥満はメタボリック症候群となりやすく、さまざまな病気を引き起こすきっかけになり得ます。
血管内に脂質が増えることで、動脈硬化になりやすいため、少しずつでも生活習慣の改善を心がけていくことが大切です。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
メディカルチェックスタジオでは
動脈硬化や血管詰まりの
起こりやすさを検査できます。
 まずは空き枠を確認してみる
まずは空き枠を確認してみる
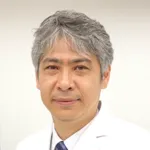
病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。


