PET検査とは? CT検査とは何が違うの? 検査後に注意することとは?
 223
223
検査の目的
PET(Positron Emission Tomography:陽電子放出断層撮影)検査は、がんがあるかどうか、がんの広がり具合、ほかの臓器への転移がないか、などを調べることができる検査です。
また治療中の効果を判定する、がんの再発がないかの確認としても行われます。
がん以外にも、アルツハイマー病、てんかん、心筋梗塞などを調べる際にも使われます。
検査の原理
体を構成する細胞は、生きていくためにブドウ糖をエネルギーとして使います。
正常な細胞ならブドウ糖は少しで十分ですが、がん細胞は正常な細胞よりも増殖を多くくりかえしているため、3~8倍ものブドウ糖が必要です。
PET検査では、ブドウ糖に極めて微量の放射線を放出する放射性同位元素をつけた薬剤(18F-FDGといいます)を体内に注射して、PETカメラ(陽電子放出断層撮影装置)をもちいて18F-FDGの全身分布を撮影します。
この18F-FDGが多く集まる部分に、がん細胞があると判断できるわけです。
CT検査との違いは?

CT検査では、検査したい部位に対してX線を浴びせるため、心臓、肺など、調べたい箇所のみを絞って検査を行います。
これに対して、PET検査は全身を一度で調べることができます。
検査のフロー
PET検査では、ブドウ糖の代謝状態を正しく捉える必要があるため、検査前には5〜6時間程度の絶食が必要となります。(水やお茶などは飲むことができます)。
検査のくすり(18F-FDG)は静脈に注射されますが、からだ全体にまわるのを待つために1時間程度安静にして待つ必要があります。
撮影はPET装置のベッドで横になっているだけです。
検査の時間
撮影自体は、30分から40分程度です。
放射線による被ばくについて
放射性薬剤を使用しますので、微量ですが被ばくします。
PET検査は一回あたり、2.0〜5.0mSv程度被ばくするといわれています。
ひとが自然に受ける被ばく線量としては、一年に2.4mSv程度といわれており、体に影響があるとされる年間の被ばく線量は、100mSv以上からといわれていることも合わせて知っておきましょう。
PET検査後の注意事項は?

検査後は通常通りの生活をしていただけますが、検査後24時間は微量の放射線が体内に残っているため、その間は授乳や乳児・妊産婦との緊密な接触は避けてください。
また使用するPET薬剤のFDGは、余った分などがおもに尿とともに排出されますので、お手洗い後は手洗いを心がけてください。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
肺・心臓・血管の状態を
調べてみませんか?
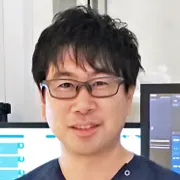
24年間の病院勤務ののち、スマート脳ドック立ち上げのためにスマートスキャンに参画。医療データ読影部兼、メディカルチェックスタジオ新宿・銀座にて技師として勤務中。
「受診者さま目線を大切にして、日々の業務に努めて参ります。」

