脳ドックとは何か? 検査の内容から受診をおすすめする方、費用、注意点まで解説
脳疾患は仕事やプライベートに大きな影響を与えます。脳梗塞や脳出血を発症すると、もとの生活には戻れない方も多いです。脳ドックは未病段階の脳の状態を把握することができ、早期発見、早期治療のために有用な検査です。この記事では脳ドックの検査内容や、見つけることができる疾患、特に受診をおすすめする方について説明します。片頭痛(偏頭痛)とは? 痛み止めと頭痛予防薬の違いについても解説!
 83
83
片頭痛とは?
片頭痛(偏頭痛)はこめかみから目のあたりにかけて、ズキンズキンと心臓の拍動に合わせたリズムで起こるタイプの頭痛のこと。
吐き気や、ひどいときには嘔吐などを伴う場合もあり、外部の環境変化(光、音、気圧、気温、湿度など)に対して敏感になる方も多いです。
発生の頻度には個人差があります。
月に1〜2回、多い方だと週に1回以上のペースで起こる方もおられます。
体を動かすと痛みが増す場合が多く、発生した際には頭を冷やして、静かな場所で横になると痛みが軽くなることが多いです。
片頭痛が起こる原因は、現在はっきりとはわかっていませんが、ひとつの説ではさまざまな要因によって脳の視床下部が刺激を受け、脳の血管を取り巻く三叉神経の周囲に炎症が起こったり、脳の血管が拡張したりすることで痛みが起こると考えられています。
片頭痛はなぜ起こるの?
片頭痛が起きるメカニズムはまだ解明されていませんが、脳の視床下部(体中のホルモンをコントロールする働きがある部分)が、刺激されているためではないかといわれています。
脳の視床下部は、自律神経、睡眠、食欲、下垂体ホルモンの分泌(性腺刺激ホルモンを含む)などを調節しています。
ですからこれらに影響を与える要素、例えば寝不足、寝過ぎ、体の過労、精神的なストレスなどが関係してきます。
また外的な環境の変化、例えば大きな音、強い光、悪天候による気圧の変化、温度・湿度の変化なども、片頭痛を誘発する要素として挙げられます。
片頭痛は男性よりも女性(とくに20代〜40代)の方に多く、出産や月経など、女性ホルモンの変化が、大きな要素として関係しているともいわれています。
片頭痛の引き金(トリガー)になること
一般的な片頭痛の引き金として、次のものがあります。
ホルモンの変化

生理期間と関係して片頭痛が起きる女性の方が多くいらっしゃいます。
また更年期障害やホルモンを使用した避妊薬などでも、誘発されることがあります。
ストレス

職場や家庭で精神的なストレスを感じると、片頭痛を引き起こす可能性が増えます。 ストレスは溜め込まないように注意しましょう。
飲み物

ポリフェノールを含む赤ワインは、過剰に摂取すると血管に作用して片頭痛の原因になります。
コーヒーなどのカフェインが多すぎる飲料も同様。
適量の摂取を心がけましょう。
感覚刺激

明滅する光、明るい光、大きな音、などがトリガーになることもあります。
香水、シンナー、間接喫煙などで強い匂いを嗅ぐことで、片頭痛を引き起こす方も一部いらっしゃるようです。
睡眠

眠りすぎ、眠らなすぎ、どちらも片頭痛の原因になることがあります。
睡眠の質に気を配りましょう。
食品

熟成チーズや食肉製品で使われる、硝酸塩やグルタミン酸ナトリウムなどの食品添加物は、片頭痛の原因となるといわれています。
天候

気圧の変化や、天候の変化によって(とくに梅雨時期の頭痛は多いです)片頭痛は誘発されます。
閃輝暗点について
片頭痛が発生する前には、閃輝暗点(せんきあんてん)と呼ばれる現象が起こる方がいることはよく知られています。
これは突然視界にノコギリ状のギザギザとした形の光が現れて、時間とともに拡大していくという事象です。

※「神経眼科 臨床のために 第2版」より引用
図のように右に半円を描く場合もあれば、反対側に半円を描くケースもあり、視界の中央に歪な円の形状で現れることもあります。
症状が続く時間は短いと数分、長い場合には1時間以上続く方も。
この症状が出ているときは、光で視界の一部が遮られ、ものが見えづらいと感じます。
やがてこめかみから側頭部にかけてドクンドクンと脈打つような痛みが始まります。
この閃輝暗点が出ているにもかかわらず脈打つ痛みが出ない方には、まれに無症状の脳梗塞になっている方もおられます。
頻繁にこの現象が起きていて、なおかつ痛みがやってこないという方は、一度MRI検査を行ってみてもいいかもしれません。

痛み止めと頭痛予防薬の違いについて
片頭痛に使われる薬は、「痛み止め」と「予防薬」に大きく分けられます。
痛み止め(片頭痛治療薬)
①一般的な鎮痛薬
いわゆる「痛み止め」といわれるもので、片頭痛以外の様々な痛みに効果があります。
中枢神経に働きかけて、解熱や鎮痛の効果を発揮するものである、と理解しておきましょう。
商品名でいうと「ロキソニン」、「カロナール」などがあります。
②トリプタン系薬剤(片頭痛専用の痛み止め)
片頭痛以外の頭痛には効果はありません。
発作が始まって30分以内に使用すると、高い効果が得られます。
片頭痛だけではなく、それに伴って起こる吐き気や嘔吐、感覚刺激に対して過敏になる現象にも効果があります。
※鎮痛薬の飲みすぎ、依存に気をつけましょう
痛み止めを頻繁に使用すると、薬物乱用頭痛を引き起こす可能性があります。
通常の痛み止めの使用は月10日を超えないようにしましょう。
1日に複数回摂取したとしても、1日とカウントして問題ありません。
日数をベースとして考えましょう。
(薬によって服用量も異なるため、薬の注意事項や処方時の医師・薬剤師の説明を守るように心がける必要があります。)
予防薬
脳の血管収縮や神経細胞の興奮を抑えることで、頭痛が起きる回数自体を減らすことにつながるのではないかと考えられています。
毎日服用していただく必要があるお薬です。頭痛のコントロールがうまくいけば、減量や服用の中止もできます。
頭痛の発作が起きたときに服用しても効果は特にありません。
まとめ

片頭痛の頻度や症状変化の内容は人によって異なるので、頭痛日記の記録を通じて、自分がどんなときに片頭痛になりやすいのかを理解することがとても大切です。
薬の服用も、しっかり体に作用するタイミングで摂取することができれば、片頭痛をうまくやり過ごすことができます。
長年ずっと片頭痛に悩まされている方の中には、まれに脳に疾患が見つかる方もいますので、検査を受けることも大切です。
頭痛外来の医師に相談することで新たな知識が得られて、ご自身の片頭痛とより上手に付き合えるようになる方もいらっしゃいます。
一度お近くの頭痛外来を受診されてみてはいかがでしょうか。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
病院に行くか迷うその前に
まずは気軽に相談してみませんか?
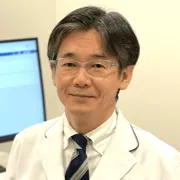
脳ドックによって脳血管疾患や脳腫瘍など様々な脳疾患を早期に発見し、早期に対応することを重視しています。生活習慣病を指摘された方や漠然と健康状態に不安を抱いている方だけでなく、健康診断で異常なく元気に日常生活を送っている方も、一度は当院の脳ドック受診をお勧めします。




