脂肪肝はどうやって治せばいいの? 血液検査だと発見できない場合もあるってほんと!?
アルコールによる肝機能障害はよく知られていますが、お酒をあまり飲んでいない方でも、脂肪肝になる方が増えています。脂肪肝は自覚症状がほぼないため、健康診断で指摘されても気にしないことが多いです。しかし脂肪肝は放置しておくと脂肪肝炎になってしまい、その後は肝硬変や肝がんになってしまう方もいます。AST・ALT・γ-GTPなどの数値は大丈夫? 肝機能検査で重要な数値について解説!
 91
91
これだけは知っておきたい、肝臓の働き

肝臓と聞くと、「アルコールを解毒するときに働いてる臓器でしょ?」と思う方も多いでしょう。しかし肝臓は、解毒作用以外でも働いています。
主な働きとしては、以下の3種類。
タンパク質の合成と、栄養の貯蔵
わたしたちが食事をすると、食べたものは胃や腸で吸収されやすい状態になり、その後に肝臓に送られます。そして肝臓ではいろいろな成分へと合成され、動脈を通って体の必要な場所へと送られるのです。
具体的には、食事から摂取された糖質はグリコーゲンになって肝臓に蓄えられ、必要になったとき(例えば夜に眠っているときなど)に使用されます。
🗒メモ
グリコーゲンとは、多数のブドウ糖が複雑につながってできている多糖類。
主に人の肝臓や骨格筋で合成されていて、筋収縮のエネルギーになったり、血糖値を一定に保つためなど、人体の中でさまざまなことに使われています。
解毒作用
肝臓はわたしたちが摂取した物質(アルコール、薬剤など)を分解して、毒性の低い物質へと変えてくれます。
また体の中では腸管にいる細菌によって、食物中のタンパク質からアンモニアが作られますが、これも無毒化してくれているのは肝臓です。
健康な人ならアンモニアは尿と一緒に体外に排出されますが、肝機能の低下が激しいと血液中のアンモニアが増え、結果として脳が障害されることもあります。
胆汁の生成、分泌
肝臓は脂肪やタンパク質の消化・吸収に必要である、「胆汁」を生成・分泌する機能があります。
具体的には、脂肪の乳化とタンパク質の分解をしており、この働きがあることで脂肪は腸から吸収されやすくなります。
また、コレステロールを体の外に排出する場合にも胆汁は必要となります。
沈黙の臓器として知られる肝臓
肝臓は働きが健康なときのおよそ30%以下になるまでは、症状となって現れてこないため、「沈黙の臓器」と呼ばれています。
ですから体に症状が現れたときには、すでに症状がかなり進行していることが多いです。
こうした特徴がある臓器だからこそ、重要となるのが健診で行う血液検査です。
血液検査でわかることは?
AST(GOT)、ALT(GPT)
ASTとALTは肝臓の機能を調べるための代表的な検査項目です。
肝臓にダメージが与えられると、細胞が破壊され、血液中にASTとALT(肝細胞で作られる酵素です)が増えます。
このことから、血液中でASTとALTの数値が高いと、肝臓が破壊されていることがわかるのです。
ASTは心臓や筋肉にもあるため、ALTが正常でASTだけが上昇しているときには、肝臓ではない場所に原因がある可能性があります。
γ-GTP
γ-GTPは肝臓の解毒作用と関係する酵素です。
肝臓の疾患以外でも、膵臓、胆道(肝臓から分泌された胆汁の通り道)の疾患でも上昇することがあります。
胆道に関連する疾患の場合には、ALP(リン酸化合物を分解する酵素)も一緒に上昇することが多いです。
γ-GTPは飲酒のしすぎ、非アルコール性脂肪性肝疾患、肝炎によっても上昇するために、肝臓に問題があることを発見することに役立ちます。
肝機能に異常があるとわかったら
健康診断で肝機能に異常があることが見つかった場合には、再度の血液検査と、画像検査をおこないます。
血液検査
・肝機能検査
・糖尿病や脂質異常など生活習慣病合併の検査
・他の肝臓病(ウイルス性肝炎や自己免疫性肝炎)の検査
・ホルモン検査(甲状腺ホルモンなど)
画像検査
・超音波検査
・CT検査
・MRI検査 など
肝臓の病気
肝臓には、以下のような病気があります。
| 病名 | 内容 |
|---|---|
| 肝炎 | 肝臓が炎症を起こして肝細胞が破壊されている状態。肝細胞が破壊と再生をくり返し、次第に硬くなり、機能も低下する。 急性肝炎と、慢性肝炎に分けられる。 |
| ウイルス性肝炎 | B型とC型が有名(A・D・E型もある)。 B型肝炎は血液や体液を媒介にして感染したウイルスが原因となる。 C型肝炎は血液を介して感染したウイルスが原因で、5年から10年かけて次の段階に進展することが知られる。 |
| 脂肪肝 | 肝細胞に中性脂肪が蓄積している状態。 多くの肝障害を引き起こす。日本人の3人に1人が脂肪肝といわれており、脂質異常、動脈硬化、糖尿病の主要な原因になりうる。 |
| NAFLD(ナッフルド) | 非アルコール性脂肪性肝疾患。アルコールやウイルスが原因ではない、脂肪肝のこと。 肥満、糖尿病など、生活習慣病が原因で増加している。 |
| NASH(ナッシュ) | 上記のNAFLDでは、肝細胞に脂肪が沈着しただけの単純性脂肪肝(NAFL:ナッフル)と、脂肪肝から炎症や線維化を伴っている、肝硬変や肝がんになるリスクのある非アルコール性脂肪肝炎(NASH:ナッシュ)に分けられる。 NAFLDの患者の20%程度は、NASHであると推定されている。 |
| 肝硬変 | 過度な飲酒や過食などで肝細胞が破壊と再生をくり返し、肝臓の表面にかさぶたのような物質ができる。これを「線維化」と呼ぶが、これが肝臓全体に及ぶと肝硬変になる。 肝臓としての機能は低下し、肝不全や肝がんにも進行することがある。 |
上記の表に記載した肝臓の病気は一例です。
お酒を飲まない方でも、NAFLD・NASHの方は増えていることが明らかになっていますので、血液検査で異常があった場合には注意が必要となります。
FIB-4 Index について
最近では血液検査項目を組み合わせて、肝疾患(肝臓の線維化)がどの程度進行しているかを調べることができる「FIB-4 index」という計算式があります。
数値が高い場合には特殊な腹部超音波検査にて評価をおすすめします。
こちらのサイトで計算できますので、ぜひ役立ててみてください。
異常値がある場合は医師に相談しましょう

肝機能に異常値の項目があった場合は、消化器内科などで肝臓の専門医に相談しましょう。
肝機能の低下が認められる場合、医師の指導のもと
- アルコールの摂取量を控えて休肝日を作る
- 適度な運動
- バランスのいい食事を心がける
- 体重を減少させる
などの生活習慣を改める療法を実践して、肝臓の病気の発症予防を行うことが大切です。
🧑⚕️こちらの記事もおすすめ🧑⚕️

編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
脳の健康状態を調べてみませんか?
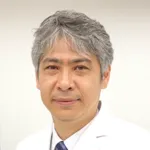
病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。


