夜になると咳が止まらなくなるのはどうして? 考えられる原因は?
熱もなく、喉の痛みもないのに、夜になると咳が出て止まらないという症状に悩まされたことはないでしょうか。にもかかわらず、医療機関へかかっても「肺や喉に異常はない」と診断されたという経験を持っている方もいるかもしれません。「なぜ夜になると咳が出てしまうのか」「自分でできる対処方法はあるか」。このような疑問について解説していきます。市販の咳止め薬は使ってもいいの? 咳の種類によって使い分けたい医薬品
 478
478
止めたほうがいい咳、止めないほうがいい咳

咳には主に乾性咳嗽(かんせいがいそう)と、湿性咳嗽(しっせいがいそう)の2種類があります。乾性咳嗽は痰が絡まず「コンコン」と乾いた咳が出ることが特徴です。一方で湿性咳嗽は痰が絡んで「ゴホゴホ」という湿った咳が出ます。
湿性咳嗽は止めないほうがいいと言われています。咳止めを使うことで痰を出しづらくなり、かえって症状が悪化してしまう可能性があるからです。そのため、咳止めではなく痰を取り除く薬を使っていきます。
一方で乾性咳嗽は、咳止めを使ってもいい咳です。
ただし無闇に使ってもいいわけではありません。
なお、夜に咳が出る場合の対処法については以下の記事をご覧ください。

咳止めの薬について
咳止めで対処できるのは「コンコン」と鳴る、痰の絡まない咳です。アレルギーや喫煙、風邪など、のどの炎症が原因で起こる咳全般に使用できます。
では、具体的にどのような咳止めが使えるのか、症状や薬の種類別に見ていきましょう。
※商品名をタップすると、製薬会社の商品情報ページに遷移します。
乾性咳嗽に使う咳止め
痰が絡まない乾いた咳には、咳中枢に働いて咳そのものを止める働きのある薬が使われます。
代表的な市販薬は次のとおりです。
【第2類医薬品】コンコン咳止め錠
「咳」は風邪の諸症状の代表的な症状です。「咳」は非常に苦痛を伴う場合が多く、 長引くこともありますので早めに治すことをおすすめします。 コンコン咳止め錠は生薬を配合し「咳」をしずめ「痰」を出やすくし、喉の負担をやわらげます。
【第2類医薬品】メジコンせき止め錠Pro 20錠
メジコン咳止め錠Proは、咳中枢に直接作用し、辛い咳の症状に働きかける非麻薬性の咳止め薬です。医薬品は、用法用量を逸脱すると重大な健康被害につながります。
ベンザブロックせき止め液
咳止め成分のほかに、痰を出しやすくする成分と喉の炎症を抑える成分が配合されています。液体なので、喉が乾燥している方向けの咳止めです。
湿性咳嗽には去痰薬
痰が絡む湿った咳には、咳止めだけではなく去痰薬を使います。
喘妙散A
3歳から服用できるお薬です。咳や痰を穏やかにしずめます。生薬成分をメインに使っていることが特徴です。
ストナ去たんカプセル
医療用のムコダインと同じ成分で、痰の粘度を下げたり過剰分泌を抑えたりする成分が主成分として配合されています。
咳止めが苦手な方には漢方薬
咳止めを飲むと眠気や便秘が気になるという方は、漢方薬を使った薬も良いでしょう。
「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒S
激しい咳が出る方に使われる漢方薬です。体力が中程度ある方に向いています。痰を取る効果もあることが特徴。
ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒
痰が絡む咳に使われます。体力が低下しており、顔が赤くなりやすく喉がイガイガしている方に向いている漢方薬。
ツムラ漢方清肺湯エキス顆粒
清肺湯(せいはいとう)という漢方薬を使ったお薬。粘り気の強い痰を伴う咳が出る方や、タバコや排気ガスなどによって咳や痰が多く出る方の、咳や痰の症状を抑えます。
トローチやドロップも効果的
トローチやドロップは、咳止めの飲み薬を使うほどではない、軽度な場合に使うことが多いでしょう。
咳止めと併用すると成分が重複することがあるので、ほかの薬との併用は基本的にできません。どうしても喉がイガイガする時は、医薬品ではない普通ののど飴を使うようにしましょう。
ペラックスイート ブルーベリーS
気管支を広げる成分と、痰の粘度を下げる成分、殺菌成分が配合されたドロップです。ブルーベリーのほかに、パインやライムの風味もあります。
浅田飴せきどめCL
気管支を広げる成分と、殺菌成分が配合されているドロップです。
コルゲンコーワトローチ
炎症を抑えるグリチルリチン酸と、殺菌成分、痰の切れを良くするセネガ乾燥エキスが配合されています。
市販薬と処方薬の違い
市販薬と処方薬とで咳止めの成分に大きな違いはありません。
ただし、市販の咳止めは様々な種類の成分が入っているものがほとんどのため、「本来なら必要のない成分まで服用してしまう」「本来必要な成分が少ない」というデメリットがあります。
必要のない成分を服用することで、副作用が起こりやすくなることもあるでしょう。
処方薬は1つの薬に1つの成分しか基本的には入っていないため、症状によりマッチしたお薬を服用できます。
市販の咳止め薬を使用する際の注意点
市販の咳止めには、使用上の注意や用法用量が記載されています。必ず飲み方を守って服用してください。薬がなかなか効かないからといって自己判断で増やして飲んではいけません。
また、服用回数を増やすのもNGです。市販薬で効果を実感できない場合は医療機関を受診して、適切なお薬を処方してもらいましょう。
市販の咳止めの中には、疾患がある方が使えない成分が含まれているものもあります。
治療中の疾患がある方は、医師や薬剤師に相談してから服用するようにしてください。
内服の咳止め薬の注意点
市販の咳止めのパッケージを見ると「咳・痰に効く」と書かれているものが多く見られます。パッケージだけでは咳を止める成分が入っているのか、去痰剤だけが入っているのかがわかりにくいのが現状です。
パッケージの裏を見て成分を確認するか、登録販売者や薬剤師に相談して選ぶと良いでしょう。
ほかのお薬を併用しないことも大切です。風邪薬、鼻炎薬、アレルギー用の薬と併用すると成分が重複する可能性が高いため、咳止めを使用している時はほかの薬を飲まないようにしましょう。
第一類医薬品として販売されている「テオフィリン」は、ほかの薬と比べて副作用が出やすいので、こちらも服用には注意が必要です。
コデイン(ジヒドロコデインリン酸塩)の注意点
市販の咳止めには、コデインリン酸塩やジヒドロコデインリン酸塩がよく使われています。
コデイン類は効果が強いとされる一方、12歳未満の方が使うと、呼吸抑制の副作用が出やすいです。小児には使えないため注意してください。
また眠気を起こしやすい成分でもあるため、服用した後は高いところでの作業や乗り物の運転は避けましょう。
便秘になりやすいことから、便秘気味の方や痔がある方は服用しないか、多めに水分を摂るようにしてください。
忙しい時に役立つ咳止め薬の工夫
仕事や育児などで忙しいと、薬をこまめに服用できないこともあるでしょう。
そのような場合には、1日1回の服用で長時間効果が持続する咳止め薬を選ぶのも1つの方法です。例えば、「12時間効果持続」「1日2回」などと表示されたものであれば、朝に1回服用することで、日中の咳を抑えることが期待できます。なお、「多めに内服すれば効果が長持ちする」ということはありません。定められた用法、用量は必ず守りましょう。
日中の業務や車の運転などで眠気が出ると困る場合は、鎮静作用のない(眠くなりにくい)製品を選びましょう。鎮静作用がある成分は「抗ヒスタミン薬」「ジヒドロコデインリン酸塩」「コデインリン酸塩水和物」などです。パッケージ表示や成分欄で、眠気の原因となる成分が含まれていないかを確認しましょう。
さらに、外出時には錠剤やトローチなど、携帯しやすい剤形の製品が便利です。咳の悪化を防ぐためには、マスクの着用や加湿器の利用などで喉の乾燥を防ぐことも重要です。限られた時間の中でも、適切な薬の選び方と日常的な工夫によって、咳による負担を軽減できます。
子どもの咳に市販薬を使う時の注意点

子どもの咳に市販薬を使う場合は、年齢に適した小児用の製品を選び、用法、用量を必ず守りましょう。大人用の薬を自己判断で少量与えると、思わぬ副作用を引き起こす恐れがあるため、注意が必要です。
特に、「コデイン酸塩水和物」や「ジヒドロコデインリン酸塩」といった成分を含む市販薬は、12歳未満の子どもへの使用が禁止されています。重篤な呼吸抑制を引き起こすリスクがあるため、購入前には必ず成分表示を確認し、不明な場合は薬剤師に相談しましょう。
子どもは症状の変化が早いケースがあります。「咳が長引く」「ゼーゼーと喘鳴がある」「顔色が悪い」といった場合は、市販薬で様子を見ず、早めに小児科を受診しましょう。軽い咳でも、夜眠れないほどであれば無理をさせず、医師に相談することが大切です。
咳が長期間続いたら
咳が長期にわたって続く場合や、市販の咳止めを数日使っても症状が改善しない場合は、医療機関を受診しましょう。咳が止まらないからといって、漫然と市販薬を服用しないことが大切です。
咳が長引く場合はただの風邪ではない可能性があります。特に発熱や無色透明でない痰が出る場合は、早めに受診するようにしてください。
咳が長引く原因については、こちらの記事もご覧ください。
咳が止まらないのはどうして? 3週間以上つづく咳は風邪ではない可能性も!
咳は誰もが経験したことがあると思います。咳というのは気道に侵入した異物を追い出すために起こる身体の防御反応です。しかし、長引く咳がある場合は病院を受診した方が良いかもしれません。この記事では、咳のメカニズムやなぜ長引くと病院を受診するべきなのかを解説していきます。
市販の咳止め薬が合っていないと感じたら呼吸器内科へ

市販の咳止めは、咳の中枢に作用して症状を抑えるものです。
処方薬と成分が大きく違うわけではありませんが、市販薬には良くも悪くも様々な種類の成分が配合されているため、症状に合う薬を選びにくいというデメリットがあります。
症状が長引く場合は、市販薬を使い続けずに早めに受診するようにしてください。
まれに風邪以外の疾患が潜んでいる可能性もあります。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
肺・心臓・血管の状態を
調べてみませんか?
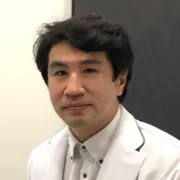
科目 内科・皮膚科・アレルギー科
2023年に千代田区神田で「スキマ時間に通える」をコンセプトとして忙しい方のために空いたスキマ時間、昼休みや仕事終わり、休みの日にも通える内科・皮膚科・アレルギー科のクリニック「クリニックファーストエイド」を開設。





