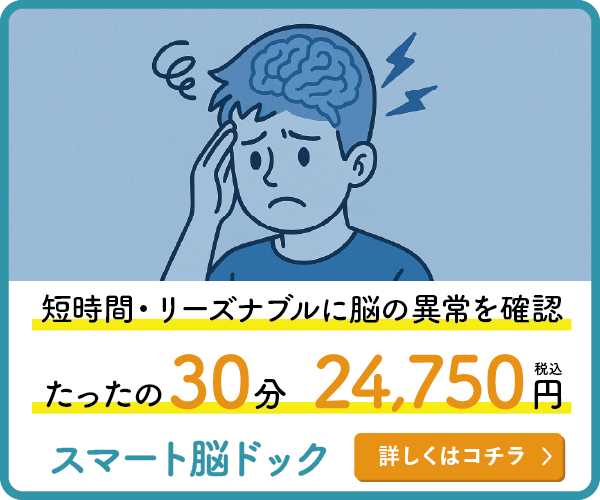高次脳機能障害とは? 診断基準、間違えやすい疾患は?(医師監修)
 47
47
高次脳機能障害とは?
高次脳機能障害とは、病気や事故などによって脳が部分的に損傷してしまい、言語、思考、記憶、行為、学習、注意などの知的機能に障害が起こった状態のことです。
よくみられる症状としては、「注意力や集中力の低下」「新しいことを覚えることができない」「感情や行動が抑えられない」「周囲にあった適切な行動を選べない」などがあります。
高次脳機能障害の診断基準
⑴ 主要症状
① 脳の器質的病変の原因、たとえば事故による受傷や疾病の事実が確認されている。
② 現在、日常生活や社会生活に制約があり、おもな原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。
(補足)
器質的病変とは血管障害、感染、炎症、変性疾患などで脳の細胞、組織が損傷を受けた病変のことです。
⑵ 検査所見
MRIやCTや脳波などによって、認知機能の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認できる。
⑶ 除外項目
① 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を有しているが、上記の「主要症状」の②を欠く場合は除外する。
② 診断にあたって、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
③ 先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする場合は除外する。
⑷ 診断
① ⑴〜⑶をすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断される。
② 高次脳機能障害の診断は、脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後で行う。
③ 神経心理学的検査の所見を参考にできる。
(補足)
神経心理学的検査とは、言語・思考・認知・記憶・行為・注意などの高次脳機能障害を数値化して、定量的・客観的に評価する検査のことです。
高次脳機能障害と間違えやすい状態は?
高次脳機能障害と間違えやすい疾患として、「せん妄」と「認知症」があります。
⑴ せん妄

せん妄はその方がもともと持っている病気や疾患、もしくは薬などの理由で一時的に意識障害や認知機能の低下が生じる精神状態のことです。
注意力や思考力の低下、日時や場所が認識できなくなる障害(見当識障害)、覚醒レベルの変動などを特徴としています。
もしせん妄になったとしても、原疾患が完治すれば予後を心配する必要はあまりありません。
⑵ 認知症

認知症はさまざまな原因で、認知機能が低下して日常生活に支障が出てくる状態のこと。
もっとも多いのがアルツハイマー型認知症で、ついで多いのが血管性認知症です。
初期は加齢による物忘れに見えますが、仕事や家事など普通にできることでミスが増え、日常生活に支障をきたすようになります。
認知症によって高次機能障害が出現することもありますが、一般的な高次機能障害とは区別されます。
高次脳機能障害の特徴
高次脳機能は精神と心理面での障害が中心になり、大きな特徴としては以下のものがあります。
- 外見上は障害が目立たない
- 本人も障害を充分に認識できていない場合がある
- 障害は診察時や入院している最中よりも日常生活や社会活動で出現する、そのため一見、気づかれにくい
高次脳機能障害を起こす疾患と症状
高次脳機能障害の原因は、大きくは脳血管障害、頭部外傷、その他にわけられます。
| 大きな分類 | 疾患 |
|---|---|
| 脳血管障害 | 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血 など |
| 頭部外傷 | 硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷 など |
| その他 | 脳炎、腫瘍、水頭症、自己免疫疾患、中毒疾患、ビタミン欠乏症など |
割合としては、脳血管障害が全体の8割程度でもっとも多い割合となっています。
高次脳機能障害で起こるおもな症状
具体的な症状については以下に記載しますが、これらの症状をあわせ持つことが多いです。
| 障害の種類 | 症状の例 |
|---|---|
| 失語症 | ・話が理解できない ・字を読み書きできない ・思うように言葉がでてこない など |
| 記憶障害 | ・物の置き場所や約束を忘れる ・物事を覚えられない ・同じことをくり返す など |
| 注意障害 | ・すぐに気が散ってミスが多い ・混乱しやすい ・集中力がない など |
| 遂行機能障害 | ・計画的に作業できない ・優先順位がつけられない ・段取りができず効率的にできない など |
| 行動と感情の障害 | ・興奮しやすい ・意欲低下 ・暴力を振るう ・思い通りにならず大声を出す ・自己中心的な行動が目立つ など |
高次脳機能障害者の生活は?
高次脳機能障害になったとしても、身体的な症状は軽度であるため、食事や排泄などの日常生活の基本部分は自立して行えることが多いです。
しかしながら、入浴、階段昇降、着替えなどの高次な作業は困難になることも多く、生活介助が必要になってしまうことも少なくありません。

「高次脳機能障害について」東京都医師会 のデータをもとに作成
脳疾患障害は予防できます

高次脳機能障害の原因としては、脳血管疾患が8割と非常に多い数値になっています。
高血圧症、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病や喫煙などで動脈硬化を進行させると、脳血管疾患のリスクは高まっていきます。
脳ドックでご自身の脳がどのような状態なのか定期的にチェックしつつ、脳血管疾患のリスクを下げるような生活習慣を目指しましょう。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
脳の健康状態を調べてみませんか?

脳神経外科専門医・血管内治療専門医
富山大学卒業後、虎の門病院入職。
東京大学脳神経外科に入局し急性期医療中心に診療に従事。
メディカルチェックスタジオ東京銀座クリニックで診療を継続する傍ら、医療業界のさまざまな課題解決のため自身でもPreMed株式会社を起業。