上皮内新生物ってなに? がん(悪性新生物)との違いは?
 220
220
上皮内新生物とは?
「新生物」は組織に通常とは異なる成長をした細胞ができた状態の総称です。
「上皮内新生物」は「上皮」といって、臓器の粘膜や皮膚の表面部分(浅い部分)に「がん細胞」がとどまっている状態です。
「がん細胞」というと怖いイメージはありますが、「上皮内新生物」がかならずしも「がん」に進行するとは限りません。
がんのステージで表すと「0期」で症状もほとんどないですが、やはり「がん」のリスクはできる限り抑えた方がいいとも考えられます。
上皮でとどまっているということは、まだ「がん」として拡がっていない状態なので、除去する負担も軽く済む傾向にあります。
「がん細胞」を早めに切除することは、将来の「がん」の可能性を少なくする意味でも大切です。
そのため「上皮内新生物」の早期発見が注目されています。
上皮内新生物の種類
上皮内新生物は上皮を構成する細胞から発生するので、肺・食道・胃・大腸・膀胱・子宮・卵巣などあらゆるところにできます。
「上皮内新生物」は「がん」のステージでは0期です。
この段階では「前がん病変」といって、放置によって「がん」になり得る状態と、「上皮内新生物」との区別をつけることが難しい段階です。
上皮内新生物がそのまま上皮よりさらに内側へと進んで大きな「がん」となるか、上皮でとどまり続けるのか、その区別がつきにくいため、「上皮内新生物」への対処が必要です。
上皮内新生物(上皮内がん)の罹患率
国立がん研究センター「全国がん罹患モニタリング集計2015年罹患数・率報告」のデータによると、がんの中で上皮内新生物(上皮内がん)と診断された人の割合は、以下のとおりです。
- 全部位、集計対象数941,419例のうち10.1%が上皮内がん
- 子宮頸部、集計対象数30,707例のうち65.1%が上皮内がん
- 肺、集計対象数106,773例のうち0.3%が上皮内がん
このデータからは、「子宮頸がん」での「上皮内がん」の割合が高いことがわかります。
上皮内新生物と、がん(悪性新生物)の違い
「上皮内新生物」は臓器などの表面部分にとどまっていることが特徴で、転移や再発の可能性は非常に低い病気です。
一方で「悪性新生物」は表面部分から奥へと進んでいき、血管やリンパ管などを侵しつつ臓器の実質へと広がっていきます。
大腸(結腸・直腸)の場合

リンパ管から「がん細胞」がほかの臓器へ飛んで、その臓器にがんを拡げることもあります。
悪性新生物は進行していき、体に大きなダメージを与える可能性もあります。
一般的に「がん」を治療する場合には、「がん」が小さい状態であればあるほど、切除などの治療をする範囲も狭く、再発の危険性を抑えられます。
大きく拡がってしまった「がん」の場合には、それだけ切除する部分も大きく、治療にも長時間を要してしまいます。
しかし「上皮内」にある病変の時点では、それが「上皮内新生物」か「悪性新生物」かの区別は難しいです。
そのために「悪性新生物」だった場合に進行するリスクを低減するため、病変範囲の狭いうちに切除を行うことがあります。
上皮内新生物の診断・治療方法
治療方法としては病変部位の切除が一般的ですが、「上皮内新生物」は病変の範囲が狭いので、切除する部分も小さくなります。
すでに拡がってしまった「悪性新生物」とは異なり、「抗がん剤」による治療を行うことはほとんどありません。
切除に関しても、範囲が狭いことから内視鏡を用いた切除術で済むケースが多く、開腹手術などに比べて体への負担も少ない傾向にあります。

「上皮内新生物」が多くみられる部位には「子宮」「膀胱」「大腸」などがあげられます。
早期発見・早期治療のためにも、これらの臓器の「がん検診」を受診することがおすすめされます。
とくに子宮頸がんでは、異形成という前がん状態を経て上皮内がんになります。
子宮の上皮内がんは数年放っておくと、浸潤が始まって拡がっていくことがあります。
上皮内新生物の再発率
病変が粘膜上層部にとどまっていますので、きれいに切除をすれば再発を考える必要はほとんどありません。
また、粘膜上層部のみにある「がん細胞」が他の臓器へ「転移」する可能性は、ほぼゼロとされています。
しかし完全に切除をしても、新たに別の「がん」が発生する可能性は否定できません。
そのため定期的な「がん検診」を受けることが重要になります。
定期的検査をおすすめします

「上皮内新生物」は将来的に「がん」に進行する「がんの種」である可能性があります。
過度な不安を抱える必要はありませんが、「上皮内新生物」として発見、切除ができれば完治します。
しかし「上皮内新生物」は臓器の表面部分にとどまるため、自覚症状がほとんどありません。
こうした病変を発見するためには、定期的な「人間ドック」「子宮がん検診」「大腸がん検診」などの受診が必要です。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
脳の健康状態を調べてみませんか?
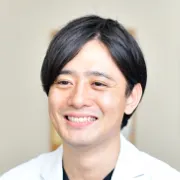
京都府立医科大学卒業後、虎の門病院入職。内科全般を学び、その後がんや慢性疾患を多く扱う消化器内科医に。『健康防衛・健康増進』の重要性を痛感。『患者様の健康増進のために本気で取り組みたい』という強い想いで、愛和クリニック開業。


