夜間頻尿に排尿痛――前立腺がんの症状とは? 検査や予防法について解説
 17
17
中高年の男性が発症しやすいがんの1つであり、自覚症状がない場合が多く、他の臓器に転移して発覚する場合も珍しくありません。
この記事では、前立腺がんの概要や主な症状、診断方法、治療方法、予防法などについて解説します。前立腺がんについて知り、がんに対する不安が解消されれば幸いです。
前立腺がんとは
前立腺がんは、前立腺に発生する悪性腫瘍です。
前立腺は尿道を取り囲むように存在し、前立腺から分泌された分泌液は精子の働きを助けます。前立腺がんは60歳以上の男性が発症しやすい病気です。
早期の前立腺がんでは自覚症状がない場合がほとんどですが、「尿が出にくい」「トイレに行く回数が増えた」などの変化があらわれる場合もあります。
前立腺がんが進行すると、血尿や排尿にともなう痛み、排尿困難などがみられる場合もあります。
また、前立腺がんは骨に転移しやすく、がんが転移した骨に痛みが生じるケースもあります。
前立腺がんのリスクを高める要因としては、前立腺がんの家族歴や高年齢などが挙げられます。
一部には食生活や喫煙などの生活習慣が指摘されていますが、現時点ではまだ明らかになっていません。
前立腺がんの予防には、定期的な前立腺がん検診が有効とされています。前立腺がん検診では、主に血液検査が実施されます。血液検査ではPSAという前立腺でつくられるタンパク質の値が正常であるか確認します。
前立腺がんの初期症状
前立腺がんの初期段階では、自覚症状があらわれにくいため、進行した後に発見されるケースが珍しくありません。
ただし、排尿の異常や血尿、血性の精液などの症状があらわれる場合もあります。
排尿の異常
排尿の異常は、前立腺がんの初期症状であらわれやすい症状の1つです。
「尿が出にくい」「急激な尿意に襲われる」「夜間頻尿(尿意を感じて夜中に何度もトイレに行く)になる」などは前立腺がんのサインである場合があります。
前立腺がんが進行すると、尿が全く出なくなるケースもあります。
前立腺肥大症でも上記のような症状がみられますが、前立腺がんと合併している可能性も考えられます。
排尿に違和感がある場合には、早めに泌尿器科を受診しましょう。
血尿や血精液
尿や精液に血が混ざっている場合も前立腺がんのサインである可能性があります。
血尿や血精液が生じた場合には、前立腺がんや腎臓がん、尿管がん、膀胱がんなどの可能性もあるため、できるだけ早めに医療機関を受診してください。
血尿の症状は、一般的には持続しにくいとされています。
症状が数日や数回で軽快した場合でも、自己判断せず、医療機関を受診しましょう。
ただし、前立腺がんの生検(がん細胞が含まれていないか観察するために、病変部分の組織を採取する検査)を受けた後では、尿や精液などに血液が混じる場合もあります。
通常、1~2週間程度で改善されると言われていますが、症状が持続したり、明らかな異常を感じたりした場合には医師に相談してください。
前立腺がんの診断方法
前立腺がんの診断では、PSA検査(血液検査)や直腸診、画像検査(MRI検査、CT検査など)、生検・病理検査などが行われます。
PSA検査(血液検査)
PSA検査は、PSA(前立腺特異抗原)と呼ばれる前立腺でつくられるタンパク質が血液中にどれほど含まれているか確認する検査であり、採血によって血液中のPSAを測定します。 PSAは腫瘍マーカー(がんがあるかの目安となる指標)として用いられており、値をもとにがんのリスクを確認します。 値が高いと前立腺がんを発症している可能性がありますが、前立腺肥大症や前立腺炎などの病気によって高まることもあります。
前立腺がんや他の疾患を鑑別するために、追加の検査が検討されます。
直腸診
直腸診は、前立腺を触って状態を確認する検査です。
肛門に指を入れて前立腺を触診し、前立腺の大きさや形、硬さなどに異常がないか確認します。がんがあると前立腺に硬くなっている部分があるので、怪しいとわかります。
直腸診で前立腺がんが疑われる場合は、画像検査や生検などにより前立腺の状態を詳しく調べる場合もあります。
画像検査(MRI、CT検査など)
前立腺がんの診断では、画像検査(MRI検査、CT検査など)が実施される場合があります。
MRI(磁気共鳴画像)検査は、磁気を用いて身体の断面画像を撮影する検査です。
主に前立腺がんの大きさや広がりなどを確認します。
CT(コンピュータ断層撮影)検査は、X線を使用して身体の断面画像を撮影する検査です。
前立腺がんの周辺臓器への広がりや他の臓器への転移の有無などを確認します。
MRI検査やCT検査では、病変部をより詳しく調べるために造影剤(血管や臓器を見やすくするための薬剤)が使用される場合もあります。
生検・病理検査
生検は、前立腺に針を刺してがんが疑われる部分の組織を採取する検査です。
病理検査では、採取した組織にがんが含まれていないか観察します。前立腺生検では診断の確率を上げるために超音波を使用しながら複数の部分から組織を採取します。
生検や病理検査は前立腺がんの確定診断に重要な検査です。
ただし、生検では感染症を発症する可能性があるため、通常、抗菌薬を使用します。
生検を受けた後に発熱をはじめとした体調不良があらわれた場合には、感染症の可能性があるため、医師に相談してください。また、生検の後は血尿が数日間見られます。あまりに長期にわたって血尿が続く場合は医師に相談してください。

前立腺がんの進行と症状
前立腺がんが進行すると、初期症状よりも明らかな異常を自覚する場合があります。 ここでは、進行した前立腺がんで起こりうる症状やメカニズムについて解説します。
進行による症状(排尿や骨への影響)
前立腺がんが進行すると、排尿時の明らかな異常や、骨への転移に伴う痛みなどの症状がみられる場合があります。
初期症状で起こりやすい頻尿や血尿に加え、尿失禁(自分の意思に関係なく尿が漏れる)や排尿困難が起こる場合があります。
排尿が困難な状態が続くと、水腎症という腎臓が腫れた状態になる場合もあり、急激に進行すると痛みが生じる可能性もあります。
また、前立腺がんは骨に転移しやすいため、骨や関節の痛みが生じるケースも珍しくありません。
特に骨盤や背骨に転移した場合には、骨がもろくなり、腰痛や骨折、神経の圧迫による手足のしびれや麻痺などを招く場合もあります。
腰痛、骨や関節の痛みが長く続いていたり、手足のしびれが生じていたりする場合には、がんのサインである可能性もあるため、がまんせず医療機関を受診しましょう。
他の臓器に転移した場合の症状
進行したがんは、骨に転移するケースが多いですが、肺や肝臓、リンパ節などに転移する場合もあります。
転移した臓器によって様々な症状が生じる場合もあります。
肺への転移は骨転移を伴っているケースがほとんどであり、転移が多発している場合も少なくありません。
ただし、咳やたんなどの呼吸器症状がみられないことも珍しくなく、胸部のレントゲン撮影により偶然発見される場合もあります。
前立腺がんが肝臓に転移すると、肝臓の機能低下による黄疸(おうだん:肌や白目などが黄色に変化した状態)や全身のだるさが生じる場合があります。
ただし、初期の肝臓転移では自覚症状が乏しいため、転移が大きくなってから発覚するケースもあります。
また、前立腺がんがリンパ節に転移している場合では、下肢のむくみを自覚する場合もあります。
排尿の異常や血尿などのサインに加え、上記の症状がみられる場合には、前立腺がんがすでに転移している可能性も考えられます。
がまんせず、可能な限り早めに泌尿器科を受診してください。
前立腺がんの治療方法

前立腺がんの代表的な治療方法としては、手術療法のほか、放射線治療、内分泌療法、化学療法、監視療法が挙げられます。
病状や健康状態を考慮して、適切な治療法が選択されます。
それぞれ確認していきましょう。
手術療法
手術療法は、前立腺がんを切除する治療法です。
一般的には、手術療法では、前立腺や精嚢(せいのう)の摘出が行われます。
リンパ節への転移が疑われる場合は、前立腺に近いリンパ節を一緒に切除し、がんが含まれていないか確認するケースもあります。
手術療法は、通常、がんが前立腺内に留まっている場合に選択されます。
手術療法では、開腹手術や腹腔鏡手術、ロボット支援下手術などが選択されます。
その中でもロボット支援下手術は、精度の高い操作ができ、出血量を抑えられるため、身体への負担が少ないと言われています。
主な合併症としては、尿失禁や男性機能障害(勃起不全、射精障害)などが挙げられます。
放射線治療
放射線治療は、高エネルギーの放射線を用いた前立腺がんの治療法です。
放射線治療は、外部照射法と内部照射法に分類されます。
外部照射法では体外から放射線を照射し、内部照射法ではシードと呼ばれる放射線を放出する線源を前立腺内に挿入します。
外部照射法と内部照射法では、適応が異なります。
前立腺に留まっている悪性度の低い早期の前立腺がんでは、内部照射法と外部照射法の両方が選択されます。
ただし、悪性度が高い場合には手術療法や内分泌療法との併用が検討されます。
放射線治療では手術療法と比べて尿失禁や男性機能障害が起こりにくいですが、外部照射法では排尿や排便時の痛みや血尿、排便時の出血などの副作用、内部照射法では排尿時に関する合併症が生じる場合もあります。
内分泌療法(ホルモン療法)
内分泌療法(ホルモン療法)は薬物療法の1つであり、前立腺がんの進行を招く男性ホルモン(アンドロゲン)の働きを抑える治療法です。
代表的な薬剤としては、LH-RH(黄体形成ホルモン放出ホルモン)アゴニスト製剤や抗アンドロゲン薬などが挙げられます。
内分泌療法は、悪性度が高く、手術や放射線治療を行うことが難しい場合や、他の臓器に転移している場合に選択されます。
主な副作用としては、ホットフラッシュ(急なほてりやのぼせなどの更年期症状に類似した症状)や性機能障害、疲労感、骨密度の低下による骨折リスクの上昇などがみられる場合があります。
化学療法
化学療法は、抗がん剤を用いてがん細胞を攻撃し、増殖を抑える治療法です。
前立腺がんでは、主にドセタキセルやカバジタキセルなどの抗がん剤が使用されます。
主に進行がんや転移した前立腺がんに対するホルモン療法により効果が得られなくなった場合に選択されます。
抗がん剤は正常な細胞にも攻撃を与えるため、副作用を引き起こす場合もあります。
代表的な副作用には、吐き気、食欲不振、下痢、感染症を発症するリスクの増加などが挙げられます。
副作用によっては、化学療法の継続が難しいケースもあります。
上記に挙げた副作用や普段と異なる体調の変化があらわれた場合には、できるだけ早めに主治医に相談してください。
監視療法
監視療法では、がんを直接攻撃するような治療が必要になるまで治療をせず、直腸診とPSAの値などで定期的な観察を行います。
前立腺がんは、他のがんと比べて進行が遅い場合が多く、不必要に過剰な治療をしないで済むことがあります。監視療法は、がんが前立腺内にとどまっていて進行のリスクが低い場合に選択されます。
監視療法のメリットは、手術療法や放射線治療などによる排尿や男性機能の低下などの合併症を避けられることです。
ただし、定期的なPSA検査によってがんの進行が疑われる場合には、手術療法や放射線治療などの治療が行われます。
前立腺がんの予防法
以下の内容に取り組むと前立腺がんの予防が期待されます。
- 定期的に前立腺がん検診を受ける
- 健康的な生活習慣に取り組む
それぞれ確認していきます。
定期的に前立腺がん検診を受ける
定期的な健康診断は、前立腺がんの早期発見が期待できます。
前立腺がんの健康診断では、一般的には、PSA検査(採血検査)が選択されます。 PSA検査による検診では、前立腺がんの早期発見や、進行の抑制、死亡率の低下が期待できると言われています。
50歳以上の中高年男性では、前立腺がんのリスクが高まるため、前立腺がんのガイドラインでは定期的な検診が推奨されています(出典:日本泌尿器科学会 前立腺癌 診療ガイドライン2023年版)。
前立腺がんの検診費用を補助する自治体もあるため、確認してみてください。
健康的な生活習慣に取り組む
健康的な生活習慣は、前立腺がんの予防につながる可能性が示唆されています。
一部には、脂肪が多く含まれた食事や喫煙、肥満、メタボリックシンドロームなどは前立腺がんとの関連性が指摘されていますが、現時点でははっきりとはわかっていません。
ただし、国立がん研究センターのがん予防に対するガイドライン「日本人のためのがん予防法(5+1)」では、がん予防に重要な生活習慣として以下の項目が挙げられています(出典:国立がん研究センター がん情報サービス)。
- 喫煙
- 飲酒
- 食生活
- 身体運動
- 体重
栄養バランスのとれた食事や、節度をもった飲酒、禁煙、適度な運動などの取り組みは、がんの予防につながるとされています。
がんを予防したい方は、生活習慣を見直すとよいでしょう。
まとめ:前立腺がんの症状と早期発見の重要性
前立腺がんは60歳以上の男性に多いがんです。
早期の前立腺がんでは自覚症状がないケースが珍しくありませんが、尿の出にくさや頻尿、急激な尿意などの症状があらわれる場合もあります。
前立腺がんの診断では、PSA検査や直腸診、画像検査などが実施されます。
治療法には手術療法、放射線治療、内分泌療法、化学療法、監視療法などがあり、進行度や健康状態などを考慮して適切な治療法が選択されます。
前立腺がんは早期に発見できれば完治できる可能性が高まります。
上述した症状が認められた場合は自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
ただし、前立腺がんは自覚症状のない場合も珍しくないため、検診を受けることも重要です。
50歳以上の方は、定期的な前立腺がん検診が推奨されています。 一度も前立腺がん検診を受けたことがない方は、検診を受けることをおすすめします。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
前立腺の異変を調べてみませんか?
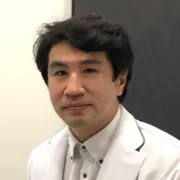
科目 内科・皮膚科・アレルギー科
2023年に千代田区神田で「スキマ時間に通える」をコンセプトとして忙しい方のために空いたスキマ時間、昼休みや仕事終わり、休みの日にも通える内科・皮膚科・アレルギー科のクリニック「クリニックファーストエイド」を開設。



