前立腺がんになりやすい人の特徴とは? 早期発見のポイントや予防法を解説
 95
95
この記事では「前立腺がんになりやすい方の特徴」「予防のために生活でできること」「早期発見のためのポイント」などを解説します。
自分や家族のリスクに気づき、前立腺がんを早期に見つけるための具体的な行動がわかります。ぜひ最後までご覧ください。
前立腺癌とは?
前立腺がんは、男性の「前立腺」にできるがんです。
前立腺は膀胱の下にある尿道を取り囲んでいる小さな器官で、精液の一部をつくる役割があります。がんの進行は比較的ゆっくりであることが多いですが、放っておくと骨やほかの臓器に転移し、命に関わることもあるため注意が必要です。
前立腺がんは年齢とともに発症リスクが高まることが知られています。国立がん研究センターによると、前立腺がんの罹患率は50代から増えはじめて60代後半から急増、70代以上がかなりの割合を占めるとしています。
前立腺がんは早く見つけることで治療法の選択肢が広がり、回復の見込みもある病気です。
定期的な検査は早期発見につながるため「自分はまだ大丈夫」と思わず、身体のサインに耳をかたむけて適切に対応しましょう。
前立腺がんになりやすい人の特徴とは?
前立腺がんのリスク要因には年齢、家族歴、生活習慣などがあります。それぞれ見ていきましょう。
年齢による影響
前立腺がんは、多くの研究で年齢との関係が指摘されている病気です。
国立がん研究センターの統計によると、前立腺がんの罹患率は50代からあがっており、60代以降でその数は急増しています。
こうした背景から、前立腺がんは早期発見のために50代から定期検診が推奨されています。
前立腺がんは多くの場合、初期では症状がありません。健康に生活するためにも「まだ症状がないから大丈夫」と思わず、年齢に応じて定期的に検査を受けましょう。
遺伝と家族歴の影響
遺伝や家族歴(家族に前立腺がんの既往がある)も、リスクに影響するといわれています。
ある研究では、父親や兄弟に前立腺がんの既往がある場合、ほかの人に比べてリスクが2.5倍以上になることがわかっています。遺伝的な要因が関係すると考えられており、家族に前立腺がんの既往がある方は、定期検診を受ける必要性が高いといえるでしょう。
予防や早期発見のためにも、まずは家族歴を確認して専門の医師に相談してみましょう。
生活習慣の影響
前立腺がんのリスクには、食事や飲酒、喫煙、運動といった生活習慣が深く関係しています。
高脂肪の食事や赤身肉中心の食生活はリスクを高めるとされ、運動不足や肥満も影響を及ぼす可能性があります。過度な飲酒や喫煙にも注意が必要です。
ストレスによって生活が乱れている場合は、バランスのとれた食事や適度な運動をとりいれるなど、生活習慣の見直しを心がけましょう。
ホルモンの影響
前立腺がんはアンドロゲン(男性ホルモン)により増殖するといわれています。
アンドロゲンとは男性ホルモンの総称で、テストステロン、ジヒドロテストステロンなどがふくまれます。男性の性徴の発達、性機能の維持、筋肉や骨の成長などに影響しており、おもに精巣や副腎から分泌されるものです。
前立腺がんの治療では、男性ホルモンの分泌を抑えるためのホルモン療法や、状況によっては精巣を摘出する手術が行われることもあります。

早期発見のポイント:前立腺がんの検査
前立腺がんは早く見つけることで治療の選択肢が広がり、回復の可能性も高まります。ここからは検査の種類や、検査を受けるタイミングを見ていきましょう。
前立腺がん検査の種類
前立腺がんの検査にはいくつかの方法があります。以下は主要な検査方法です。
PSA検査
血液中の前立腺特異抗原(PSA)の値を調べる血液検査で、多くの医療機関で行われています。数値が高ければ前立腺がんの可能性があり、さらなる検査が必要になります。
直腸診
医師が肛門から指を入れて前立腺の状態を直接触って調べる方法です。前立腺表面に凹凸がないか、硬いところがないかなどを確認して、異常があれば前立腺がんを疑います。
画像検査
画像検査では、必要に応じてMRI検査、CT検査、骨シンチグラフィなどが行われます。
「MRI検査」は、磁気を利用して身体の中を立体的に映し出す検査です。がんの位置や大きさ、転移の有無などが正確にわかります。
「CT検査」は、X線を使って身体の断面を撮影する検査です。前立腺だけでなく、リンパ節やほかの臓器への転移を調べるために使われます。
「骨シンチグラフィ」は、がんが骨に転移していないかを調べるための検査で、前立腺がんが進行している場合に有効です。
前立腺生検
ほかの検査で前立腺がんが疑われる場合、「がんである」という診断を確定するために前立腺生検がおこなわれます。前立腺の組織をいくつか採取してがん細胞の有無を確認します。

検査を受けるべきタイミング
前立腺がんの検査は「いつ受けるか」が大切です。年齢や家族歴など、自分のリスクに応じて適切な時期に受けることで、早期発見につながります。
一般的には、50歳を過ぎた男性には、年に1回の定期検診がすすめられています。これは、50歳から前立腺がんの発症リスクが高くなるためです。
前立腺がんは遺伝的な影響もあると考えられており、家族に前立腺がんの経験があると発症リスクが高まることが知られています。そのため、前立腺がんの家族歴がある方は、40歳ころから検査することがすすめられています。
前立腺癌の治療方法
前立腺がんの治療には様々な方法があり、がんの進行具合や広がり、患者さんの体調や希望によって決まるものです。ここからは具体的な治療方法について見ていきましょう。
手術療法
手術療法では、前立腺と精嚢を取り除いて膀胱と尿道をつなぎあわせる「前立腺全摘除術」が行われます。具体的な方法は以下のとおりです。
開腹手術
開腹手術は腹部を切開する手術で、全身麻酔と硬膜外麻酔を使用して行われます。手術には3〜5時間かかり、1〜2週間の入院が必要になります。
腹腔鏡手術
下腹部に5〜12mmほどの小さな穴を数か所開けて、専用の医療機器を挿入する手術です。開腹手術に比べて身体への負担が少なく、術後の回復も早いとされています。
ロボット手術
下腹部に8〜12mmの穴を数か所開けて、手術用ロボットを遠隔操作しながら行う手術です。腹腔鏡手術よりも精密で、開腹手術よりも身体への負担が少ないといわれています。
これらの手術療法によってがんを取り除くことで、長期的な生存率の向上が期待できるでしょう。
なお、手術後には尿漏れや性機能の低下といった合併症が起こる可能性もあります。治療を選ぶときは、こうしたリスクも踏まえて医師と相談しながらすすめることが大切です。
放射線治療
放射線治療は、外から放射線をあてる「外部照射療法」、身体の中から放射線をあてる「組織内照射療法」に分かれています。
外部照射療法
外部照射療法は、身体の外から前立腺に放射線をあてる方法です。
近年はコンピューターにより、照射部位を制御できるようになっており、周りの臓器への照射量を減らせるようになってきました。一般的に1日1回週5回照射して、1ヵ月半ほどの期間で治療でき、外来受診でも治療可能です。
組織内照射療法
組織内照射療法は、体内からがんに放射線をあてる治療です。数日間の入院が必要な治療で、放射線を出す小さな粒を前立腺のなかに埋め込むため、ピンポイントで効果を発揮します。
どちらの治療も、頻度や時期は異なりますが「頻尿」「おしっこが出にくい」「排便時に痛みがある」などの合併症が起きる可能性はあります。治療前に医師としっかり話し合い、納得して治療をすすめましょう。
ホルモン療法
ホルモン療法は、前立腺がんの進行を抑えるための治療法の1つです。
前立腺がんは男性ホルモン(アンドロゲン)によって成長する性質があるため、このホルモンの働きを抑えることで、がんの進み方を緩やかにするのです。
ホルモン療法に用いる薬にはいくつかの種類があり、注射や内服薬などにより治療が行われます。ホルモン療法は前立腺がんに有効な治療ですが、これだけで完治するのは難しく、ほかの治療と組み合わせて行われることもあります。
なお、長期間にわたってホルモン療法を続けると、血栓ができやすくなったり、心臓や血管の病気が引き起こされたりするリスクもあるため、注意が必要です。治療中は定期的に検査を受け、医師と相談しながら安全にすすめていきましょう。
その他の治療
前立腺がんの治療には、手術、放射線療法、ホルモン療法のほかにもいくつかの選択肢があります。
例えば化学療法はがんが進行していたり、ホルモン療法が効かなくなったりした場合に行われる治療法です。抗がん剤を使ってがん細胞の増殖を抑えることを目的としています。
また「骨」は前立腺がんにより転移しやすい部位の1つです。転移している場合は「骨修飾薬」とよばれる、骨転移を抑える薬を使用することもあります。
前立腺がんを予防する生活習慣とは?
前立腺がんのリスクを減らすためには、日々の生活習慣を見直すことがとても大切です。特に意識したいのは「食事」「運動」「禁煙・節酒」「ストレス管理」といった基本的な生活の部分です。それぞれ、具体的なポイントを見ていきましょう。
食生活の改善
前立腺がんの予防には、バランスのとれた食生活が欠かせません。
特に、リコピンを多く含むトマトや、大豆製品、野菜を中心とした食事が役立つと考えられています。リコピンは前立腺の健康維持に効果が期待でき、大豆製品に含まれるイソフラボンはホルモンバランスを整えるサポートをしてくれるのです。
また、緑茶やコーヒーにふくまれる成分には抗酸化作用があり、体内の炎症を抑える働きがあるといわれています。
一方で、脂肪分の多い食事は前立腺がんのリスクを高める可能性があるため、注意が必要です。油を多く使った揚げ物を控えて、蒸し料理やグリル料理など、脂肪を控えた調理法に切り替えるだけでも、身体にやさしい食生活に近づけるでしょう。
適度な運動と体重管理
運動不足や肥満は前立腺がんのリスクを高める要因です。
肥満だと進行がん(大きく広がる、またはほかの部位に転移しているがん)のリスクが高くなるという報告もあります。
ある研究によると、運動だけでなく家事、仕事、移動などの身体活動により前立腺がんのリスクが低下することが示されています。
体重を管理するためには継続的に運動を続けていくことが大切です。ほかの生活習慣とあわせて、日常生活にとりいれやすい散歩(ウォーキング)をはじめ、家事や通勤などを通して活動量を増やしていくとよいでしょう。
禁煙・節酒
喫煙や過度の飲酒は、前立腺がんを含む多くのがんのリスク要因です。
喫煙本数、喫煙年数が多い男性は前立腺がんのリスクが上がるとされています。また、欧州のある研究では、ヘビースモーカー(25本以上/日)もしくは、40年以上の喫煙歴がある方は、前立腺がんでの死亡リスクが高くなるとされています。
飲酒も、がんが大きくなったり周囲の組織に広がったりする「進行がん」のリスクが高くなる要因とされています。これはエタノールが分解されたときにできる有害物質や、アルコールによる性ホルモンへの影響が関係していると考えられています。前立腺がんのリスクを減らすためには、喫煙や飲酒を控えることを心がけましょう。
ストレス管理
ストレス管理も前立腺がんの予防には大切です。
長期的にストレスを感じている方は、前立腺がんのリスクが高くなることがわかっています。また、ストレスが大きいほどリスクが上がることもわかっています。
ストレスは、食生活の乱れや飲酒、喫煙などの生活習慣にも影響する要素です。日常生活の中で「好きなことをする時間をとる」「散歩や運動してみる」など、心が休まるタイミングをつくり、ストレスを軽減するように心がけましょう。

まとめ:前立腺がんの特徴を理解し、予防を心がけましょう
前立腺がんは年齢、遺伝、生活習慣などがリスク要因とされており、早期発見には定期検診が欠かせません。高齢になるにつれて罹患率が上昇するため、50代以上の方は注意が必要です。
前立腺がんの予防には、生活習慣の見直しが大切です。バランスのとれた食事、適度な運動、ストレス管理などを心がけて健康維持につとめましょう。小さな積み重ねが、未来の自分を守る力になります。
編集部までご連絡いただけますと幸いです。
ご意見はこちら
スマホでかんたんスマートに。
前立腺の異変を調べてみませんか?
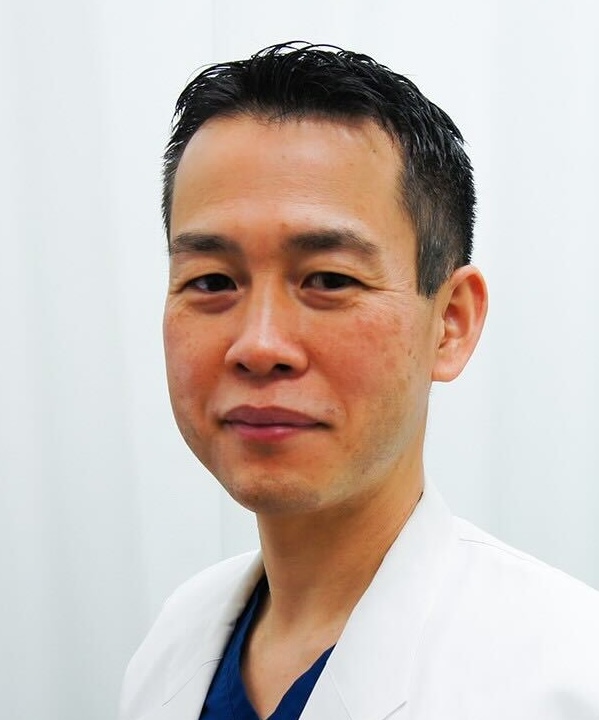
その後、2014年2月にさいとう内科クリニックを開院。



